artscapeに関わっている主要スタッフの方々:発信元のDNP ICC本部(本部長・加藤恒夫氏、志村耕一氏)とサイトを運営しているDNPアーカイブコム(原瀬裕孝氏)、サイト開設以来のメインライターでもある美術ジャーナリスト・村田真さんに話を伺った。
学生:岡田伊央、河野通義、佐藤美保、じゃんゆんそん、ぱくちゃんほ、藤川知佳 今西彩子 : 本日は、大日本印刷のメセナ活動、そしてそれに纏わる企業のイメージ戦略やマネジメントについていろいろお聞きしていきたいと思っております。
加藤恒夫:まず、メセナの最近の動向についてご紹介しましょう。 岡部あおみ:どうして福島県の郡山に開設なさったのでしょう。
加藤:CCGA(現代グラフィックアートセンター)の隣にあるゴルフ場を当社が所有していたのです。 岡部:gggは86年に開設し、CCGAは95年に創設されたわけですが、活動として双方の関わり合いはあるのですか?例えば、gggは企画だけでコレクションには関わらず、CCGAはいわゆるケネスさん関連企画だけにしぼっているといったような・・・。
加藤: タイラー・グラフィックスの契約は面白い契約でしてね。お金を払っているのは、アーカイブを引き受ける際の最初のお金だけなんですよ。その後は10エディション以上のものが出来上がると、ひとつだけ作品を無料で送ってくる格好になっています。
岡部:彼のコレクション美術館みたいなものですね。
加藤:そうです。その代わり私たちはCCGAのタイラー・グラフィックス作品を売買することは出来ません。うちの会社がおかしくなって、どこかに処分しなければいけないときは、私たちが引き受けている条件をそのまま引き受けてくれるのところに移さなくてはいけない。ただ、残念ながら3年前にマウントキスコのタイラー・グラフィックス工房は活動を終了しました。今はシンガポールで活動されていますけれども。もう増えていくことはないと思います。このままになると思います。
岡部: gggの企画方針はどういったものでしょう。
加藤:一番最初にこのギャラリーをつくる際に田中一光さんにご相談をして、先生の方からグラフィックのギャラリーをやったらいいんじゃないかという話があったものですから、ずっと田中さんの監修でやっていました。田中先生とご相談をしながら、年間企画を立てていくという恰好にしていましした。しかし残念ながら2002年1月10日に田中先生が亡くなられてしまいましたが、まだ宿題が2年分くらいありますものですから、今その2年分くらいの宿題をいかに消化するかということに腐心をしているところです。
岡部:展覧会は大体1ヶ月に1回ペースですか?
加藤:そうです。特別展を催すこともありますけれども、1ヶ月に1本、年間で12本です。その中には定期もので、団体展が2つ入っています。1つが東京アートディレクターズクラブ(ADC)の展覧会で、リクルートの「クリエーションギャラリー」との共同開催でやっています。それからもう1つは浅葉克己さんが監修されている東京タイポディレクターズクラブ(TDC)の展覧会です。秋には、「Graphic Wave」という大体3人の作家による定番の展覧会企画があります。
岡部: 共同企画みたいなかたちで一緒にやる方が半分くらい運営費を持ってくれるのでしょうか?
加藤:いいえ持ちません。
岡部:全部主催者が持つのですか?
加藤:はい。当社では作品の制作費は原則として持ちませんが、開催告知と会期中の運営管理に関しては全部うちが持っています。
岡部:すごいですね、100%メセナのかたちですね。
加藤:gggの信頼性が高くなった一番の要因は、多分アニュアル・レポートを作ってきたからだと思います。通常、デザインのギャラリーではあまりアニュアルをつくっていませんし、今の美術館・博物館関係の方もなかなかアニュアルをお作りにならないですね。わたしたちは、ggg開設後3年目からアニュアル・レポートを作っています。
岡部:レポートを初めて拝見したときは驚きました。活動内容とレポート自体の立派さに。
加藤:ものすごくお金がかかってるんですよ。しかしやっぱりアニュアルを作っていくことは私たちの記録の整理にもなりますし、それをある時系列で見てみると、デザインの変化とかが見えてくるというのはありますね。 今西:先ほど運営理念が設立当初とは変わってきたとおっしゃられましたが、先頃オープンした「メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランス」もその移り変わりの中で発生してきたのでしょうか?
加藤:印刷会社では、さまざまな印刷物をつくっています。フランスの美術館との関わりというのは、例えばセザンヌなどの泰西名画のカレンダーをつくるという中で発生します。私たちは、さまざまな企業のカレンダーを企画、撮影、印刷からすべてやります。その中でフランスの美術館との関わりが随分増えていきました。一方、出版社は美術全集も作ります。そこでは編集企画は出版社が立てますけれども、作品の撮影はどのようにしようとか、どうやって許可を取ろうとか、そうした実務的な問題は私たちが担当しているケースが多いわけです。 岡部:他にギフトの品物には何を多く使われますか?
加藤:大体複製彫刻ですね。
岡部:サモトラケのニケとかですか?
加藤:はい。親しくお付き合いをさせて頂いているところにはブロンズ製を、多少お付き合い程度のところには樹脂製を、という感じですね。現代のもの、例えばタイラー・グラフィックスの作品を差し上げてもなかなか理解し難い感がありますので、その点銅版画などはどなたにもあんまり抵抗なく理解できるのかな、と思って最近そちらにシフトしてきています。 岡部: フランスのRMNはかつては全然なかった東洋系のグッズも最近は作って販売していますね。
加藤: あれはギメが3年ほど前にリニューアルして、ルーヴルオリエントという位置づけになったからです。今はギメのグッズも随分増えてきています。 今西:先程、品物をわかってくれる人にだけ、口コミなどで来ていただいて売るというメゾン・デ・ミュゼ・ド・フランスの姿勢のお話がありましたが、大日本印刷の子会社も含めて、特にトランスアートもそういう志向なのでしょうか。例えばトランスアートでは絶版になった本を復刻されたりしていますよね。
学生:私は実際に武井武雄の『紀田順一郎セレクショ ン 製本』というトランスアートの復刻版を買いましたが、絵本みたいに見ても楽しいですよね。
加藤:あの本はよく売れました。 岡部:完成という諦めがつかないですよね。
加藤: デザインの世界もそうですよ。殆ど諦めがつかない。 今西:よく今の出版産業は自転車操業的な回転をしていると言いますよね。
加藤:自転車操業になればいいんですけど、危ない状況ですね。大手の書店さんはまだいいのですが、地方の中小書店さんが非常に苦しくなっています。それから、オンデマンドの最大の欠点は、少ししか売れませんから、広告を打てないので、どうやって知らせるかというのが一番のネックです。いまヨーロッパですと、ミュージアムの展覧会図録がオンデマンドになりかかっているという状況です。細かいこと言いますと、通常、日本の印刷は殆どオフセット印刷ですが、プレートレス印刷になるとオフセット印刷と違ってグラビア調という諧調で印刷しますから、そういう点では深みが違って品質的には面白いです。 今西:オンデマンドに関して、復刻をやるか新刊を出すかの違いはあれども凸版印刷と足並みを揃えていらっしゃいますが、凸版との違いはありますか?
加藤:技術的には変わりません。ビジネス・スタンスとして私たちは「本とコンピュータ」というプロジェクトから入っていますから、どちらかというと出版社サイドで、もしくは編集者や作家のサイドから提案をしていくという形になります。凸版さんの場合は東京出版販売という販売ルートと組んでやっていますから、どちらかというと流通側からということになりますね。日版もそうです。私たちのスタイルは、アメリカの大学出版に近いかなとも思います。マーケットとして、どういう風に立ち上がってくるのかわからないところがある分、各社がさまざまな努力していけば良いのだと思います。
今西: 凸版の印刷博物館はどう思われますか?
加藤:一生懸命やっていると思いますね。去年は、トッパンホールをメセナ賞で表彰させていただきましたけれども、非常に頑張っていると思います。 今西:村田さんにお聞きしますが、アートスケープにレビューをお書きになる時に、紙メディアに書く時との違いはどこで意識されますか?
村田真:アートスケープに関わることで意識し始めたのですけれども、それまではずっと手書きにこだわっていたんですよ。パソコンなんか一生いじらないんじゃないかと思っていたくらいなんです。 今西: あまりこねくり回すことなしに直接的に文章をお書きになっているなということを、とても感じているのですが。
村田:いろいろお叱りも受けますけれども(笑)。
加藤:話し言葉的に文章が出て行くという感じで起承転結の構成がしにくいんじゃないですか?
村田:どうやってつじつまを合わせるのかというと、つじつまが合わないこともあるし、いわゆる筆が滑るということも多々あります。それも紙メディアにはない良さというか、特長として捉えていきたいなと僕は勝手に思っていますけれども。最初からインターネットとかはもっとラフにやっていっちゃっていいんじゃないかということを思っていたんですよ。紙メディアは残るということがあるから、すごく慎重になってしまいますが、インターネットで書く場合はもうがらりと発想を変えちゃいます。
岡部:たまに直してくださいと言われたりすることもありますか。書き直しをなさることはないですか?
村田:出したものは変えないですね。
岡部:サイトだと、基本的にいくらでも書き直すことは出来るわけなんですけどね。
加藤: 紙メディアではレイアウト原稿の字数が決まってきますが、インターネットの場合はないわけですよ。紙メディアでは、ちょっと多いから5行くらい削ろうとか、ちょっと膨らまそうとか出来ますが、インターネットの場合は特別で、電話の話し方とそう変わらないんですね。
村田:ずるずる出していいメディアというのは他にちょっとないような気がしますね。いいのかな、こんなに出しちゃって、いう感じがあります。
加藤:あまり制約ないですしね。放送のように時間的な切りがあるわけでもないし。
村田:とにかく枚数は何枚くらいというのはないですからいくらでも書いていい。書こうと思えば際限なくずるずる引き出して書けちゃうから。
岡部:自分で字数制限をするのですか?
村田:はい、そうですね。
今西:逆にその方が読む側にとっては親しみやすいという感はありますね。別にパソコンの前でかしこまって読むわけでもないですから。
村田:本を読むほどにはしっかり読んでくれないだろうということが予めあって、こちらとしても書き流したいと思っています。
加藤:それはあるかもしれないですね。例えば学芸員の人の書いた文章って精巧で、わけのわからない論理展開があって読みたくないじゃないですか。あれは紙メディアだからじゃないかな。インターネットで学芸員の文章みたいなあんな難しい用語は出て来ないし、あまり辞書なんか引かずに変換でやっちゃいますもんね。
今西:ジャーナリストとしてのお立場から、普段からアートスケープに書くにしても他の紙メディアに書くにしても、通底して持っていらっしゃる重要な観点はありますか?
村田:清く正しく美しくというやつで、自分に対して嘘や不正確なことは書かないようにするというくらいでしょうね。後はあまり自分の立場を固定したくないので、批評的な観点が固定しないようにすること。だけれども、一人の人間でも時とか気分とか立場によってぶれると思うんですね。だから批評的な観点はその時々でぶれてかまわないと思います。そういう意味では、自分の立場をこれだ、という風になるべく持たないようにしています。 加藤:アートスケープはペーパーメディアと違ってすごくインタラクティブになって、割合反応が早いじゃないですか。リアクションがあったりしたときに、美術ジャーナリストとしてはどうですか?
村田:リアクションのことで言うと、アートスケープも書いてからアップされるまで2週間くらいかかります。もっと早いと思っていたんです。原稿を出してから、デザインやその他いろいろな作業があって大変みたいですけれども、反応はあるにしても直接的に僕の方に来るというのは少ないので、意外に紙メディアとそれほど変わらないです。アートスケープに関しては、読みましたよ、という意見は沢山聞くんですよ。それは他の紙メディアに書くよりも多いです。時折、非常にプライベートなことも書いちゃって、それを全然知らない人が知っていてびっくりしますが。
今西:村田さんが書いた文章は、ICCの編集部に送られるのですか?
加藤:そうです。校閲が大変なんですよ。
今西:文章の編集とサイト自体の更新は本当に大変だと思うのですが、メンテナンスはどうされてるんですか?
加藤:デジタルアーカイブもありますし、無所属の方と一緒にスタッフプロジェクトチームを組んでいます。そういう人たちとは、進行管理や情報共有が非常にしやすくなっていますが、いろんな問題も出てくるので、そういうところは編集がやっています。
今西:アートスケープのコンテンツは誰がお考えになったんですか?他では見られないような美術用語や美術館条例などの情報が多数満載ですけれども。
志村耕一:コンテンツはアートスケープをやっていくうちに段々と増えてきましたね。今のアートスケープには大きな流れが二つありまして、ひとつはミュージアム・インフォメーション・ジャパンというDNPホームページに美術館の基本的な情報を集積させるという試みです。その頃、93年当時というと、インターネットのイの字くらいだったんですね。一方、我々と美術館の関係者有志とで、“美術館をもっとメディアとして進化させよう”という「美術館メディア研究会」を立ち上げました。これには、岡部先生にもゲストスピーカーとして登壇いただきました。インターネットが出てきた状況を踏まえて、研究会の中では、もっとオープンで、情報発信力のある美術館が出来たら美術館も面白くなるだろうということになって、その刺激づけも含めて立ち上げたのがインターネット・サイト「ミュージアム・インフォメーション・ジャパン(MIJ)」です。研究会の中には現役の学芸員の方も何人かいらっしゃったのですが、インターネットで美術館は何ができるか、ということをメディア側の我々と関係者の方々とがコラボレーションしながら美術館の情報を集めていくうちに増えていって、その結果やれることも増えていったという経緯があります。
原瀬裕孝:もうひとつの流れが、96年に開催されたインターネット・ワールドエキスポです。インターネットは既に世界的に知られてはいましたけれどもユーザーというのはほんの一握りしかいなかった時代に、インターネットが世の中をどう変えていくのか、ということをアメリカを中心に、日本では慶応SFCのMr.インターネット・村井純さんなどが推進役となりましてネット上で博覧会を開催することになりました。DNPとしてもパビリオンを立ち上げ、ネットによる新しいコミュニケーションの世界を探ろうということで積極的に参加していきました。パビリオンというのはインターネットサイトを立ち上げることで、DNPとしましては、インターネット上に美術館を作ってみようという世界初のアート企画を提示しました。インターネットにおける全く新しいアートワークのアワードを開催したり、それまでネットとは関わりのなかった作家をネットの世界に招待して、新たなアートワークをコミュニケーションの視点から実践してもらったりしました。そうした一連の活動の中で、美術館として情報を交換し発信するジャーナルが必要だよね、という話から、「ネットワークミュージアムマガジンプロジェクト」(nmp)という、ウェブマガジン形式でのアートマガジンの発行を始めました。その後、ミュージアム・インフォメーション・ジャパンと融合しまして、今のアートスケープに至っているということです。
今西:96年のインターネットワールドエキスポでは、色んな市や企業が独自のパビリオンを繰り広げていましたけれど、美術に特化したパビリオンはなかったですよね。
原瀬:あの頃はネットワークが作る新しいコミュニケーションとビジュアルネットワークというものが世の中をどう変えていくのか、ということをアートフォームとして提示するというかたちで作品化して頂こうと思いまして、例えば招待作家のお一人オノ・ヨーコさんの作品は、オノ・ヨーコさんがネット上に一日に1本づつ100日に亘って提示するインストラクションに、世界中からその実践報告を返信してもらい、返信そのものもデーターベースとして蓄積し、それを誰もが閲覧できるというプロジェクトで、それはコミュニケーションが新しい表現になるというコンセプトの一つの実践であったわけです。おかげ様で世界中からさまざまな反応を頂いていたんですけれども、その流れが継承されていったのがアートスケープなんですね。
岡部:ダイレクトに読者からメールが来たりしたのですか?
志村:作家、あるいはジャーナリストがメールをくれることもありますし、こんな展覧会やっています、というような、いわば投稿ページみたいなものもあります。
今西:かなり個人的な投稿もあるのですか?
志村:基本的にはアート情報サイトということでお分かりは頂いているので、展覧会や出版、あるいは公募展みたいなものの情報を頂きますね。
岡部:投稿する人の意見や感想のようなものはありますか?
志村:いえ、特に情報が多いですね。
今西:自由に投稿出来て閲覧も出来るような掲示板は今のところ作らないのですか?
加藤:意見投稿に関して言えば、非常に難しい問題で、修羅場になる可能性があります。意見の決闘場になったり、2ちゃんねるみたいになってしまうので、出来るだけ本体からは放しておいて個人の課外活動でやっていただいた方がベターかなと思っています。
岡部: 現在はライターや編集者として、何人くらいの方がアートスケープに関わっているんですか?
志村:村田さんは除いて、常時コアなメンバーとして10人くらいです。村田さんはレギュラー執筆陣ということになっています。
岡部:今回事前にアートスケープのサイトを知っているかとか、利用しているかに関するアンケート用紙を頂いたのですけれども、ああいう利用者アンケートは時々されているのですか?
志村:up date newsというサイトの更新情報をお知らせするメールサービスがありまして、その折にご意見を頂くことはありますね。
加藤:難しいのは、企業イメージなのか何なのかわからないところです。うちの場合、ある意味こういう企業形態ですとビジネスに変わっちゃうんですね。ビジネスに非常に近い接点にありますでしょう。例えばアートスケープがアートスケープでやっているうちにそのシステムを横展開して仕事を引き受けてくれませんか、という話になってきますよね。
原瀬:僕は本業で全国の美術館の方々と新しいコミュニケーションシステムの開発、みたいな話がよくあるんですけれども、初対面の学芸員の方からも、「アートスケープ見ていますよ」というお話をいただきますので、アートスケープをやっているDNPという面で見ていただいていることが多いですね。
加藤:逆に言うと、情報が集まりやすくなってくるということが言えます。アートスケープを経由して集まってくるというビジネス上の利点はあります。そこのところは非常に悩ましいところでビジネスなのかメセナ活動なのか・・・基本はメセナ活動なんですがね。 岡部:モーターになってるんですね。
加藤:かなり理想的に、両輪のように進んでいく。例えば美術館博物館を運営していく中で、それこそ情報化していくと、どうしてもお金が要りますよね。データを入れていくにしても、スキャナーを買わなきゃいけないしパソコンも買わなきゃいけない。そうすると、そのお金はどうやって作っていくのか、となると、あるビジネスモデルを提案し、ある経済サイクルを作っていくことは結構必要なことになります。文化というアイテムのビジネスモデルです。そこは文化政策学の視点を持っていないと出来ないですね。 今西:長い時間ありがとうございました。他に意見や質問などがありましたらどうぞ。
学生:私はこの間から武井武雄の本や、「アートと社会の縁結び」というトランスアートの本を買ったりして、今までなかなか身の回りにはなかったものを手に入れたのでとても嬉しく思っているのですが、それが最近、例えば東京都写真美術館の本が普通に平置きで置かれていますよね。今まで注目はされているけれどもオリジナルはすぐに手に届かなかったり、図書館にもなかなかなかったりする中で偶然その本を見つけて、こんな動きがあるのかと、とても嬉しく思ったのですが、この分野で他にどんな可能性があるのでしょうか。
加藤:オンデマンド出版の可能性のことで言えば、例えばペーパーメディアですと全集から全集を買わなくちゃいけないというのがあるわけですよね。しかし、デジタル化されていればそれを一部分でも取り出すことが出来るし、それをディスプレイで読むことだって出来るし、それをPDFデータにすることによってもいろんな展開の可能性を持っています。
学生:取り扱う文章について、取り上げるジャンルはある程度方向性が決まった上でのことですか?
加藤:全然決まっていません。さっき言ったように、全集の中の解説文は本として世の中に出て来ることはないわけです。しかしデジタル化の中では解説文だけを出してくることが出来る。デジタル化構想の中で一番面倒臭いのは、文字をどうするのかという問題で、例えばユニコードの漢字は日本、台湾系、韓国系、中国系の4つのスタイルがあります。日本の場合そういうものは、異体字という囲いの中でいろいろありますよね。それをビジュアルで取り込んじゃうのか、データで取り込んじゃうのか、またある程度それを世の中に出していったときにどう受け入れられるのかといったことが問題です。
学生:村田さんがアートスケープに書くことになったきっかけは何ですか?
村田:水戸芸術館の学芸員の森さんという方から誘われたんです。
志村:森さんは、岡部先生にもゲスト講師をお願いした「美術館メディア研究会」の最初からのメンバーでいらっしゃって、面白い人は面白い人を知っている、ということですね。
今西:雑誌「ぴあ」のアート欄立ち上げに関わったと聞いておりますけれども、そのころからメディアとアートについてお考えでいらっしゃいましたか?
村田:いえ、全く考えていませんでした。「ぴあ」に入ったのは卒業してすぐのことで、それまで僕は美大で絵を描いていたわけですけれども、とにかく美術に関わる仕事を探していて、そしたらたまたま「ぴあ」が美術欄を募集していて、受けたらたまたま入っただけなんですね。美術に関わる仕事なら雑誌でも何でもよかったんです。それが今に繋がってきていて、だから最初からメディアとか全然考えていなかったです。それにやっぱり未だに僕の目標はアーティストなんですね。アーティストが一番偉いなと思っていますし、出来ればアーティストになりたいという思いはずうーっとあります。それは今の書くモチベーションになっているかもしれないです。
学生:アートスケープのレビューですと、沢山の人がアクセスして村田さんの文章を読むと思うんですけれども、村田さんはコンピューターの向こう側で読んでくれている人を想像されたりするんですか?
村田:それは殆どないですね。書いているときは、ある一人の人を想定することはあります。この人にこの文章は通じるだろうか、この人ならこれで笑ってくれるかな、とかいった具合にある人を想定したほうが書きやすい。実際に読んでくれる読者というのはどんな人だろうとかは全く考えないです。お客様は神様としか意識してないですね。つまり要するに意識していないということです。
加藤:最近問題なのは、学生さんのレポートが情報の羅列になってしまっているというケースです。インターネットで情報だけを集めてきて、その集積のみで解析がないまま、それがレポートになってしまっているということが私たちの世代でよく言われているんですね。集めた情報を自分の論理構造の中でいかに解析してレポートにしていくのか。ある主題の元で、理論構成していくとなると特にコンピューターはちょっとつらいところがありますね。情報の集積だけを画面上で読まされるのはちょっとつらいな、と思います。例えば自然科学系ならそれでいいと思うんですね。しかし人文科学系となると、ある解析というか、自分なりのこなし方が必要になってきて、表現していかなくちゃいけない。我々がアートスケープでやっているのは、ひとつの断片情報を出しているということです。ですから、きちんとした論文は載せられないですよね。その辺のウェブの使い方は難しいところかもしれません。
今西:おっしゃる通りで、我々がアートスケープの情報を受け取り、それを深めていけばいいわけですよね。アートスケープの中には批評の欄がありますが、文章としては短く、ウェブで読まれるのには適度な分量で、我々がそのきっかけ材料を各々使いこなしていかなければならない。そういう点からアートスケープは読み甲斐があるなと思います。村田真氏・加藤恒夫氏・志村耕一氏・原瀬裕孝×岡部あおみ・今西彩子
日時:2003年7月4日
場所:銀座、大日本印刷 ICC本部
01 大日本印刷DNPのggg(スリージー)とCCGAの創設
つい先日『メセナマネジメント』という本が企業メセナ協議会から出ました。
最初の頃のメセナというのは宣伝活動や、企業イメージをPRするような意味合いが非常に強かったように思います。しかし最近では、文化経済学や文化政策というジャンルやメセナ活動が変わってきています。特にバブル以降の日本経済の中では、地域間格差の問題あるいはモノ作りがなくなりつつあるという問題があって、特に地方都市では文化を基軸にして経済をつくっていこうという文化政策的な考え方が入ってきています。従来の考え方では文化政策というのは、国や都道府県や市町村などの行政がやるものだと言われてきました。ところがNPO設立などの動きが出てくるなかで、企業や行政がNPO組織と一緒になって文化を形成していこうという動きになって来ています。こうした動きが、最近盛んになり、それが地域の町おこしや村おこしといったものに繋がってきています。
私は今、企業メセナ協議会が主宰するメセナ大賞のまとめ役をやっています。今年も約120件ちょっとの候補案件が出てきました。傾向としては、単独のメセナよりも共同メセナが目立ってきています。例えばトヨタの「エーブルアート協会」のようなNPO組織もありますし、住友海上では名古屋の自社ビルで人形劇のサークルと常設の小屋を持ち、運営は人形劇団に一任しつつ、そこに社員が参加するといった活動を展開しています。要するにメセナの形は従来とは非常に変わってきていて、特にここ数年目立った変化が見られます。メセナという言葉自体は、1992年に「企業メセナ協議会」が発足して以来広まった言葉なので、まだかなり新しい言葉です。
次に当社の活動についてお話ししましょう。ggg(ギンザ・グラフィック・ギャラリー)が誕生したのが1986年です。80年代というのは社会が大きく変わった時期です。「生活者」という言葉が一般的になったのは80年代初頭のことです。そのときに公害問題や企業の超過黒字の問題、かたや企業活動が不透明で分りにくいというわけで、さまざまな批判や非難が出ました。その批判に対して企業側が私たちはこんなことをしていますよ、という自己表明が始まり、「企業市民」という言葉が出てきました。
私たちがgggを始めました頃、当時一般の方にとっては、印刷会社は具体的に何をやっているのかは知らないわけですね。せいぜいマンガ雑誌の裏に大日本印刷と書いてあるとか、教科書の裏に大日本印刷と書いてある、というくらいの認知度だったわけです。印刷工場といえば、オジサンがバタンバタンと機械を動かしているようなイメージがせいぜいで、小学校の社会見学で新聞社の印刷工場に行って輪転機をスゴイなあと思って見るといった感じでしょうね。でも私たちの印刷の仕事は、町の中にあるポスターやカタログ、スーパーマーケットにある食品のパッケージや化粧品のパッケージ、それから建物や家具の建造材料、電子部品など身近な暮しの多分野にわたっているのです。
私たちの会社を、就職を考える学生の方をはじめ、一般の方たちに理解していただくにあたり、デザインと印刷との関わりを皆さんに見ていただこうということではじめたのがこのggg(ギンザ・グラフィック・ギャラリー)です。
その後、福島県の郡山には、CCGA(現代グラフィックアートセンター)を開設しました。版画などのいわゆる複製芸術、グラフィックアートにも印刷会社が関わっていることを理解してもらおうというのが主旨です。版画は、いわば印刷の原点でもあります。
CCGA は1990年にアメリカの方からお話がありました。ケネス・タイラーという版画の刷り師がいて、彼は西海岸の版画工房のトップクラスの刷り師でした。その後、西海岸の財産を全部放り投げまして74年に東海岸のニューヨークにタイラー・グラフィックスという版画の工房を開きました。マウントキスコという、なかなかいい別荘地で、秋に行くと紅葉が美しくてアップダウンが多い土地です。そこでケネス・タイラーはフランク・ステラやヘレン・フランケンサーラーなどのクリエイター達とのコラボレーションで現代版画を作ってきました。タイラー・グラフィックスは、アメリカのミネアポリスにあるウォーカーアートセンターにもアーカイブされていて、それをアジアに展開したいから、引き受けませんかという話になりました。ちょうどそのとき、全く別件で横浜の美術館でケネス・タイラーの展覧会をやるという話がありまして、それなら借りてくるよりもうちが買っちゃったものをお貸しした方が楽なんじゃないかということになって、急遽アーカイブコレクションとして買いました。「アーカイブ」というのは記録的時間的保存ということです。
タイラー・グラフィックスの創立から現在までに制作された作品の10エディション以上の内、エディションナンバーが入っているものも含めて800点くらい引き受けました。1年半程、日本全国の美術館の展覧会で巡回しました。展覧会が終わった時点で、将来ワークショップをやろうという構想もあったので、アーティスト・イン・レジデンスの計画も含めて検討した結果、福島のゴルフ場のそばに土地があるからそこに作ろうということになりました。作品の収蔵を主体にしつつ、展示のスペースももたせたが福島のCCGAです。
建てるに当たって、アメリカの現代版画を入れるんだから、アメリカの景観計画を取り入れた設計にしようということで、アメリカ人に基本設計を頼みました。さすがに凄まじい現代建築になりました。こうした経緯が福島のCCGAにあります。
最初は当社を理解してもらおうという意図でつくったgggも今年で17年過ぎました。いまでは、逆にグラフィックデザインの中で世界一有名なギャラリーになりました。すると、gggで展覧会をやることがトップステージに上がっていくことだ、というステータスが生まれてきたのです。しかしそうなると段々使命が変わってくるんですね。毎月1回展覧会を開催します。展覧会のオープニングパーティには、日本のトップデザイナーの方が必ず見えます。するとそこが情報交換の場になってサロン化していき、さらに出品作家による「ギャラリートーク」など企画を増やしていくとグラフィックデザインというものに対して段々と理解が深まっていきます。最近は美術大学の学部の方でここに来てレポートを書くと単位が貰えるという講座があるそうです。
企画運営がマンネリにならないように、一方ではいかに壊していくのかを常に心掛けたいと思っています。今の時代をいかに見るのかという提案をしながら、来て頂いた方の反応やリアクションを受け止めて、それをまた何らかのかたちでデザインに反映させてゆくというサイクルだと思います。

ggg 内観 photo Mitsumasa Fujitsuka

CCGA 内観 photo Mitsumasa Fujitsuka
02 メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランスのギフト商品
90年代から表現技術が紙から電子媒体に変わってきました。私たちは、その前から画像をデジタルで処理して印刷するスタイルを取っていました。そのデジタル処理したデータを使って、フィレンツェやルーヴルやオルセー、国内だと東京国立博物館の国宝シリーズのハイビジョン画像やソフトを作ってきました。それは作家別のものもありますし、美術館別のものもあります。ルーヴルには、ペーパーメディアとハイビジョンの番組を作りませんか、と申し出ました。そのなかで、フランス国立美術館連合(RMN)との関係ができました。そうこうしているうちに、インターネットが普及し、デジタル化した画像やデーターベースをどういうふうに扱っていくのかということが時代の課題になったわけです。 フランス国立美術館連合という組織にはフォトエージェンシー部門があります。そこにはフランスの国立美術館33館の作品のポジフィルムがあってそれを貸し出しています。つまりライセンスを所持しているわけですね。その後、デジタルに関わるビジネスを日本で展開する、という話になりまして、「RMNイメージアーカイブセンター」を設立しました。 しかし、デジタル画像に特化したビジネスというのは、当時まだまだ早くて、CD‐ROMやDVDがいろいろ出たりしていますけれども、通信の問題で、いい画像を送ろうとしても重くて送れないという状況がありました。私たちが始めた時にはまだブロードバンドが出来ていませんから、細々としたインターネットの回線で送るのには15分とか1時間とか待たされるわけで、それならばと、CD‐ROMにもしたんですけれど、CDもOSが変わると開けなくなるという技術的なハンディキャップもありました。
情報というのはリアルなものがまずあり、ペーパーメディアがあり、デジタルメディアがあってそれらがお互い行き来しながらある関係を作っていくのだろうと思います。一番困るのはイタリアですよね。イタリアにはいい作品がいっぱいあるんだけれども、ほとんど教会美術だから、それをはがして持ってくるわけにはいかない。やはり現地に行かなくちゃいけない。私たちはある意味で、美術全集などのメディアで「システィーナ行きたいだろう。ルーヴルのあの階段登りたいだろう、あの三角の屋根に行ったら気持ちいいぞ」というような欲求不満をつのらしているようなものです。
しかし印刷ではもうひとつリアルな感じでものや質感はなかなか伝わりませんから、それどう伝えていこうかと考えた時に、レプリカグッズが展覧会で売られている状況を見て、それを逆に展覧会というイベントでではなく、日常の中に持ち込んでみたらどうだろうか、というビジネスコンセプトでやってみようということになりました。ものだけを売るということでは、三越がメトロポリタンミュージアムグッズを売り、ギャランティーが高かったせいで大失敗したケースがありましたけれども、当社では、情報を乗せてみようと思いました。情報とは、具体的には、彫刻の本物はどこに置かれていて、作家の作品はどういうふうに分散していて、どういう交通アクセスがあって、入場料はいくらで、何時から何時までやっているのか、というような情報です。実際、ルーヴルに行く前に本を買うのは大変です。ですから、そういう情報を付加する機能をもたせたのです。そしてgggの隣のビルを買って始めたのが、メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランス(MMF)です。2002年11月のことです。
RMNは国立美術館の33館だけが管理下でした。もともとあの組織は、グラン・パレがオープンした際に、展覧会の運営を担当するためだけの組織だったんですね。そこで展示をやったり、カタログを作ったり、入場者の切符を売ったり、もぎったりするところからスタートしたのがRMNという組織です。一昨年フランスの美術館・博物館法が大幅に改正された際に、ミュゼ・ド・フランスという名前で再編成しました。それまでの美術館・博物館法というのは日本の美術館・博物館法の管理基準に割りと近い形だったんですけれども、改正した際に国家として評議委員会を作りました。国公立や市町村立の美術館・博物館、歴史建造物、資料館が必然的にミュゼ・ド・フランスの傘下に入ります。そしてミュゼ・ド・フランスという冠を被せてもらう代わりに、各館は社会教育への参加の要請を受けますが、一度傘下に入ると、潰れてしまったときに競売に伏すことが出来なくなります。いわゆる財産権の保全ですね。
メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランスという名前は「ミュゼ・ド・フランス(RMN)の館」という意味です。メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランス自体、今はもう赤字です。グッズそのものは売れていますけれども、絶対に安売りせず、やせ我慢してもお客を選んでいくという方針ですから大々的な宣伝はしておりません。しかしその代わり、例えば企業同士の多少のお付き合いの中で、事務所を開いた際のお祝いなどのコーポレートギフトには、お馴染の胡蝶蘭がたくさん並ぶ中で、私たちは銅版画などを贈らせて頂いています。これはこれで宣伝になっていて、ワンパターンの胡蝶蘭ばかりの中で銅版画を貰うと、「これどうしたんですか?」と聞かれるわけです。すると、「これはうちで売っていますよ」という話になって、実際にメゾン・デ・ミュゼ・ド・フランスという場所が出来たものですから、来てくれるわけです。
メゾン・デ・ミュゼ・ド・フランスは11月にプレオープン、次ぎの年の2月にグランドオープンし、非常にリピーターが増えています。最初は3500円くらいのカメオや帽子を買われます。最初買わない人でも2回目くらいに来たときに、そういうものを買ってくれます。するとお友達に「変わってるんじゃない?」と言われて、「これはどこそこの美術館のもので・・・」という話で話題になりますよね。「じゃあ今度一緒に行ってみようか」という話でお友達を連れていらっしゃる。そういった口コミや、あるいは販売スタッフとのコミュニケーションもあって、フランスに行ってレプリカの本物を見てくる。またはお友達へのお祝いにうちの商品を差し上げようなどと、段々とそういう輪が広がっていく。
マスセールスによって広がっていくのではなくて若干わかって頂ける方に来て頂いて、口コミで広がった方がいいのかなと思います。今は東京だけで商売をやっていますが、いずれはこれを日本全国に広げていこうかなと考えています。そしてそれを今後アジアにどう展開していくのかということも課題になっています。
私自身も中国の仕事をしていますので、中国の方とも、そういったものの交流をどのようにしていくのか、ということが課題です。
10年程前、上海博物館が今の新館になるときに、ハイビジョンの100インチ大画面設備一式を寄付しました。今は非常にいい博物館です。そして博物館のミュージアムグッズも非常によくなってきています。
今は中国のものをフランスに、フランスのものを中国に、という橋渡しをしています。特に、2008年に北京オリンピック、2010年に上海万博、そして一昨年にはWTOに加盟をしたということで、非常に国際交流や文化交流が盛んになっていて、それがまた購買力となってきています。そこが非常に面白いなと思っています。ここであるプロトタイプを作って、それが使いやすければ、他のところにのって頂くというようなことを進めていきたいと思っています。先の長い話なので私が会社にいる間には儲かりそうにもありませんね。
03 トランスアートの復刻本とオンデマンド・プリント
トランスアートという会社自体の生い立ちを話しますと、1992年に設立した会社です。今は私が社長をやっています。91年にgggをリニューアル・オープンした際に、小売の会社を作りましょうということになってできたのが、トランスアートの始まりです。アメリカのブリキ美術や、アメリカの現代版画を売ったりしているうちに、gggの出展作家の本も欲しいという話になり、「gggブックス」を作りました。
「本とコンピュータ」という本も季刊で刊行することになりましたのは、現在和光大学の教授をされている津野海太郎さんという方がいらっしゃるのですが、その弟さんがたまたま私の上司で、その上司とこれからのデジタル化の中で文学というものをどういうふうに捉えていこうか、という話をしているうちに出てきたことです。研究会をやったりしたらいいんじゃないかという話も出たのですが、それよりも本を出そうということになって、世の中に評価してもらうために定価をつけて本屋で売ろうと、誕生したのが季刊「本とコンピュータ」です。
印刷はやっていますけれど出版社をやったことはなかったので、gggブックスも通常の出版ルート通さないで、六本木のブックセンターなどアートに詳しいところにお願いして置いてもらったというのが、その当時の状況でした。創刊をしたのが7年位前ですね。
そのときのテーマはいろいろありました。一つはディスプレイで小説が読めるかという問題です。ゴシックで行間も何も無いようなもので文芸ものなんて読めるわけがない。漢字やひらがなやカタカナがある日本語がディスプレイの中で今後どうなっていくのかという問題がある一方で、私たちはディスプレイも作っていますから、ディスプレイの再現技術や文字の問題を考えなくちゃいけない。二つ目は、電子図書館の問題をどうするか。これもちょっと大変で、OSが変わったのでパソコンの博物館になってしまうのではないかという危惧もあります。紙媒体であれば、何年何月に発行というように固定されますけれども、電子情報では、いくらでも書き換えがきいてしまうわけです。
ほかにも、視覚的・生理学的な問題としては、透過光と反射光の記憶層に対する頭脳とのインターフェースの問題もあげられます。そうこうしているうちに出版不況になってきました。ある時、朝日新聞社の主催でスウェーデンの詩人作家協会の方を呼んできて講演をやりました。その中で、どうも世界ではオンデマンド・プリントが流行っているらしいという話がありました。フランスでは、00h00.com(オーホー)というオンライン出版がスタートしています。アメリカでは大学出版協会で教科書のオンデマンド・プリントを始めて、設備としてはIBMやゼロックスがオンデマンド・プリントのためのテキストデータのシステムを作りました。印刷技術的な話では、プレートレス・プリントも登場しました。従来の方法ではプレートがあってプレートにインキをつけたものを転写していくのですが、プレートがなくなって、電子体の中でそれを転写していくというような方向に少しずつ変わってきています。システム化が進み、オンデマンドのハード面での整備が少しずつ揃い始めているから、やってみようということで「HONCO on demand」をスタートさせました。
このシリーズでは、必ずしも復刻に限定せずにローマ字ものや、詩集ものをやりました。そんななか、天皇皇后両陛下がスウェーデンを訪問されるにあたり、スウェーデンの俳句協会と俳句集をオンデマンドで国際出版しようという話になりました。スウェーデン語の俳句を五七五に直して、日本語の俳句をスウェーデン語に直して出版するのです。日本ではスウェーデンの文字を作れないですから、向こうで一式作ってもらって、日本の文字はこっちで作って、それをPDFデータにしてお互い交換するという出版実験をやりました。 次に手掛けたのが文芸出版社6社との共同出版です。岩波、晶文社、白水社、みすず、筑摩書房の6社と組んでオンデマンド出版で何が企画できるかやってみようということではじめました。なかには全集ものの前書き、解説文だけを集めるという面白い企画がありました。各社ともいろんな企画を集めて「リキエスタ」という統一シリーズ名前で刊行しています。今一番売れているもので2000部くらいですね。今、出版業界は非常に景気が良くありません。その中にあって、新しい出版の形を提案できれば、という思いでやっています。
オンデマンド出版を復刻版に限定した分野では、凸版印刷と東販(東京出版販売)で組んでいる「デジタルパブリッシングサービス」という会社があります。ビジネスとしてはそちらの方が多いでしょう。他には、日販(日本出版販売)と出版社で組んでいる「ブッキング」という会社がありますけれども、そちら方もリクエストのある本を復刻するという前提でやっています。私たちの方はどちらかというと、新刊の方にシフトしています。
早稲田大学のオンデマンド出版シリーズも、わたしたちが手掛けています。最近は大学でも教室に行かずに、自分の都合に合わせて、インターネット上の講義にパソコンを使って参加することで単位が取得できるネットワーク授業が登場しています。こうした授業でもテキストはやはり紙メディアの方が読みやすいし、使い勝手も良いのですね。そこで授業の教科書や参考書をオンデマンド出版するというケースも出てきています。
また「デジタルアーカイブ推進協議会」という研究団体があって、私も参加していますが、そこで刊行する白書を、会員以外の方でも入手できるよう、オンデマンドで販売するということも行われています。
このように、これまでは大量生産・大量販売が基本だった出版産業も、次第に変わって来ているのです。
今、日本では、年間6万4000タイトルの新刊書が出ています。ということは約1日で200タイトルですね。その初版平均販売部数が1800部くらいです。そして本屋さんは約3万軒あります。書籍の実売率は大体40%程度になっています。本が売れない状態にあります。

ggg ブックス © DNP
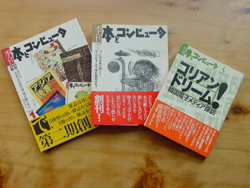
「本とコンピュータ」 © DNP
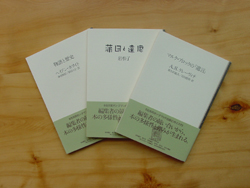
「リキエスタ」 © DNP
04 凸版は官 大日本は民
印刷は、それをどういう切り口で見ていくのかというところが非常に難しいんですよね。ひとつはこれを産業史的に見るという見方があります。近代印刷が出来たのは1450年にグーテンベルクが42行聖書を刷ったのが始まりと言われていますが、それから日本に一度入ってきて、イエズス会が布教のためにキリシタン大名の少年使節団に印刷道具一式持たせて帰し、そして天草で昔物語や天草草紙という布教書を作ったのが大体16世紀くらいの頃で割合早い時期です。それが豊臣秀吉のキリシタン廃止で全部捨てられてしまった。改めてもう一度入ってきたのは1850年代の終わり、あるいは1860年代の最初の頃で、これが江戸幕府の時の長崎造船所、今の三菱重工のオランダ語通訳をやっていた本木昌造という人が印刷編集所を作った時ですね。そして明治期に築地活版所を作り、産業広告的な情報ということで活版印刷が始まったのですけれども、段々それが商業的に引き札、今で言うとチラシやパンフレットの類が出来てきて、それが錦絵だったり、木版だったりします。そこからタバコや石鹸の包装紙などのパッケージに使われていき、段々と産業との関わり合いの幅が広くなっていったということがあります。さらに第二次世界大戦後になると建材やアートに繋がってくる。このように、印刷を産業的にどう見ていくのかという見方が1つあります。
もうひとつの見方として、印刷は情報を伝えていく手段であるというメディア論的な見方があります。そのどっちをとるか、ということでだいぶ方向性が変わります。そういった点で、凸版さんはもうちょっと自分たちの歴史を整理したらいいんじゃないかなと思います。
私たちはもう少しメディア的な見方をしつつ、現在のデジタルメディアに印刷というものがどうつながってくるのかということを考えていきたいなと思います。古い話になると日本では木版画の歴史があったりした後に写真技術が入ってきたりと複合的になってきています。そういうところをもう少ししっかり見ていったらいいんじゃないか、そこのコンセプトが弱冠曖昧なんじゃないかと、彼らと議論していますが。ただ非常にいい活動をしていると思います。
凸版印刷は1900年創業なんです。私たちが1876年の創業です。凸版印刷は1900年に、表向きは大蔵省印刷局の肖像画を担当していたキヨソーネのお弟子さんたちが作った、というふうに言われている会社で、どちらかというと官制の会社ですね。1900年頃はベルギー条約調印の問題や、日露戦争の戦費の後始末問題で、法律的に専売法というものが出来て、塩やタバコの専売が出来た時代です。タバコの専売の頃、京都の村井商会という一番大きな会社では刻みたばこを作っていたのですが、大蔵省がそれを全部買収して、初めにそのパッケージを作ったのが凸版ということになっています。私たちはどちらかというと民の方、凸版は官の方ですからそこの違いはありますよね。
05 アートスケープにはずるずる出す
たまたまご縁があって書き始めた時、最初は手書きで原稿を出していたのですけれども、それではさすがに都合が悪いので、ようやく重い腰を上げてパソコンを使い始めました。始めた以上、手書きとは変えたいというか、変えなくちゃいけないだろうし、当然変わってくるだろうと思ったんですね。アートスケープに関わり始めたのが96年で、パソコン買ったのが97年です。パソコンに全く知識がなかったものですから、素直にやっていくうちに、手書きというのは考えていることと書いている内容との間にワンクッションがあるんだと気付きました。それに比べてパソコンはもっとダイレクトに脳と繋がっているなというイメージがあって、書いていくうちに頭の中にあるものがずるずる出て行っちゃうという感じがします。だからアートスケープではなるべく正直に脳にあるものをずるずる出していこうという気持ちで書いています。
そこら辺が評論家とは名乗りたくない理由だと思います。ジャーナリストもしっかりした観点を持っていないといけない部分があると思うんですが、もうちょっと流されてみるというか、流れてもいいんじゃないかと思います
06 ミュージアム・インフォメーション・ジャパン(MIJ)
07 メセナか情報産業かの境界の難しさ
冒頭に言ったみたいに、この問題はどういうサイクルを作るのかというきっかけだけなんです。 アートスケープは後ろから押してあげる力が多分にあるんで、それに対してどういうエンジンになるかということなんですね。
何かと上手くいかないところが多いですよね。メセナはメセナであるわけじゃないですし。今まで美術館の方たちというのは、新聞社に頼って来たわけです。私はお金は触りませんよって綺麗事言ってね。しかし、いざ独立行政法人になったら自分で運営しなくちゃいけない。新聞社に任せてきたそこのお金をどうやって捻出していくのかという問題は、今はアメリカが一番進んでいますけれどもね。
本日は長いお時間を頂きありがとうございました。
(テープ起こし担当:今西彩子)
↑トップへ戻る

| top | about CP |