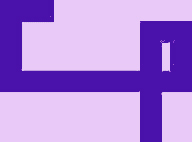イントロダクション
ベルリンには今、刺激的な都市の胎動がある。各国からアーティストがぞくぞく集まってきているのも、その徴候のひとつだろう。芸術の都は、パリからニューヨークにかわり、さらに21世紀の「アートの解放区」、ベルリンに移りつつあるのかもしれない。
ベルリンのミッテ地区にある画廊街に、やなぎみわの画廊もある。元マーガリン工場を改修したクンスト・ヴェルクを主会場に、第三回ベルリン・ビエンナーレが2004年に開催された。ビエンナーレの開催期間に、ドイツ・グッゲンハイムでは、やなぎみわの個展が開催されていた。ドイツ銀行ベルリン支社の建物の一階をアートスペースにして、ニューヨークのグッゲンハイム財団が共同で運営にかかわり、新作を含むやなぎの充実した写真展の展示作品のほとんどが、ドイツ・グッゲンハイムの収蔵品というから驚きである。
個展の出品作の1枚、若い女性に50年後の自分の姿を想像してもらった「マイ・グランドマザーズ」シリーズ、「Mineko」の写真が、鉄道の駅をはじめ、ベルリンの至るところに華々しく掲げられていた。グライダーを操縦する老女のイメージで、どことなくやなぎ自身の面影も宿している。パリにも画廊をもち、世界各地で活躍する作家となった作家が大空を背にする勇姿。20代の女性たちとともに未来の女性力を示すポジティヴな夢の象徴を制作している。またそうした方向と平行して、新作の寓話シリーズでは、歴史のDNAのように心理の奥深くに刷り込まれた少女のトラウマを描いている。ポジとネガの大きな振幅が、やなぎのヴィジョンをより手応えのあるものへとシフトさせている。
ベルリンの個展の図録に、上野千鶴子が執筆していた。ベルリンで今回の二人のトークを思いついたのだから、20世紀の歴史的な舞台となったドイツとベルリンが二人を引き合わせたようなものだった。多産な学者、上野千鶴子の論文や著書は膨大な数に及び、その影響力ははかりしれない。社会学という「虚学をなりわい」とし、時代の生理を体現しつつ、シャープな分析と認識を通して創造力豊かに新たな言語を編み出す。かつて歌人の訓練を積んだことがあるというが、上野千鶴子のことばはつねに端的で先鋭で、かつ暖かい。
おそらく20冊ぐらいは楽しく読破してきた上野ファンのひとりだが、やなぎみわの「Mineko」が表紙となった『ことばは届くか』(上野千鶴子X趙韓惠浄 岩波書店、2004年7月)は、心にみずみずしい力が湧いてくる本だった。日本と韓国のフェミニストの往復書簡という画期的な形式をとりながら、繊細な翻訳者の努力もあって、当事者の上野が心踊る体験だったと回想するのと同じ感覚が読者にも伝わってくる。趙韓惠浄(ヘジョン)ファンにもなった。世界にはじつにすてきな女性がいるものである。
「ことばは届くか」という問いには、希望と困難がこめられているという。このサイトを見てくれているあなたたちには、きっと「ことばは届いている」に違いない。
(岡部あおみ)