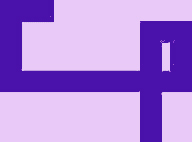コメント
この講義録は、後に雑誌『あいだ』91号に、「身体の表現―エロスと暴力の現場として、あるいは……」と題されて載せられた。何もなければ一介の聴講生としてその場を過ごしたであろう私は、『あいだ』の編集者の方に頼み込んで、第一次テープ起こしをさせて頂いた。おかげでテープ起こし以上のいくつかのことを勉強させて頂いた。と同時に、講義と質疑応答の現場記録を反芻することによって、芸術社会学の視点は、批評の世界において意外にもマイナーなのではないか、ということを感じた。萩原先生は講義の中で、作品の中に描かれるものの見方、感じ方というものをすでに私たちは社会の中で教育されているのだ、という旨を幾度か繰り返されており、それに反対を表明する立場の人との問答があった。私にとっては、普段見ることのないその問答が新鮮な光景であった。そうした現場に立ち会って、初めて私自身の批評の立場を客観的に見ることができたように思う。
芸術社会学とは、なるほど、イメージの渦から社会的なある共通認識と思われる記号を抽出して言語化しようというのだから、虚学中の虚学なのだろう。絵を描くというのは人類の原初的なコミュニケーションツールであり、表現である。言葉を覚える以前に子どもは絵を描く。つまり、イメージは完全に言語化できない性質のものであるにもかかわらず、なおも人間社会に通じる記号を抽出して言語化しようとする理由は、私たちは自分が知っているようにものを見がちである、という事実側面を否めないからである。また他方で、自らの経験則を頼りに社会的な共通認識を抽出するのにも、注意しなければ独りよがりになることから、多くの人の賛同を得るまでは空気を手でつかむような作業である。それでも、私などはそのような批評の仕方へと興味が赴く。なぜなら、究極的には私という存在の不可解さを考えることに繋がるからだ。このように私は何の役にも立たない動機で、肥大化した自己意識を持て余しながら学問を続けているが、少なくとも人間が築いた共通認識を可視化させ、現実の問題として投げかけていくことは社会的に価値があるのだろうと信じている。
萩原先生は、性別・身体・エロス・人種をテーマに、私たちが教育されたものの見方を鮮やかに浮き彫りにされている。何度も反芻して見習いたい。
(今西彩子)