インタヴュー
野村誠(アーティスト)×岡部あおみ
参加者:芸術文化学科学生・院生、他学科学生・教員、オープンキャンパスに訪れた高校生など
日時:2010年6月13日
場所:武蔵野美術大学
岡部あおみ:今日は一日高校生が参加するオープンキャンパスです。芸術文化学科の「現代アート研究」という講義と、大学院で今年はアジアのアートシーンを研究しているのですが、その「芸術文化政策演習」の二つの合同授業のモデル講義として、野村誠さんにレクチャーをお願いしました。 今回の講義のタイトルに「カルチャーパワー」とあるのは、10年ほど前に芸術文化学科が創立した時から、学生たちと一緒に、100人以上のアーティストやキュレーター、ギャラリストなどのインタービューを手掛けてきて、それをウェブサイトの「カルチャーパワー」にアップロードしており、今回の野村さんのレクチャーもこのウェブサイトに掲載する予定だからです。ですので、もし野村さんのレクチャーを最後まで聴けない方がいても「カルチャーパワー」と、カタカナ、あるいはアルファベットで検索していただけば、トップに出てきますので、そこで野村さんの話を最後まで聴くことができるようになっています。 会場にいらっしゃる高校生で、将来なにか文化に関わる仕事をしていきたいと考えている人たちにとって、たとえばキュレーターという仕事をしている人はどんなことを考えているのか、あるいはギャラリーを自分で立ち上げた人はどういうことに苦労しているのか、そういった実際の体験談がこのウェブサイトではヴィヴィッドな形で読めますのでぜひ参考にしていただければと思います。 では野村誠さんを簡単にご紹介致します。野村さんは京大の理学部で数学を学んでいらっしゃいますが、小さい頃からずっと作曲もされていて、ピアノも弾かれますが、鍵盤ハーモニカの第一人者でもあります。アートの分野でも広く活躍されていて、横浜トリエンナーレなどの国際展にも参加され、アートと音楽の境界でもっとも先鋭な活動をされている方ですので、今日は幅の広いお話が伺えられればと思います。それでは、よろしくお願いします。
野村誠:今日はオープンキャンパスでいろんな人が出入りする可能性があるということなので、できるだけぶつ切りで話題を変えていきながら、僕のパフォーマンスの映像もたくさん見つつ、繋がっているような、いないような感じで進めていけたらと思います。
01 『お湯の音楽会』
野村誠:ぼくは音楽家/作曲家ですが、ご紹介にあったように随分多くの国際展に参加しています。昨年は、「福岡アジア美術ビエンナーレ」に参加していたんですけれども、その時に発表したものに、『お湯の音楽会』があります。

「お湯の音楽会」DVD (09)
かつて神戸の六甲山で、キャンプファイヤーの音を聴く『火の音楽会』を開催したことがあり、その時は、火の中にマイクを仕込んだり、アルミ管を使った聴診器を火の中に突っ込んで音を聴いたりしたので、『水の音楽会』をやりたいと思っていましたが、『水の音楽会』を実現する前に、『お湯の音楽会』をやることになりました。『お湯の音楽会』は、銭湯でお湯を演奏するコンサートをしよう、という発想から始まりました。日本には銭湯という場所があって、男湯と女湯に分かれています。みなさんは行かれたことがあるでしょうか。昔ながらの番台があって、男湯と女湯があって、上が抜けているような、そんな銭湯がだんだん世の中から姿を消しています。福岡市内で探したところ、もう数えるほどしかありませんでした。その代わりにスーパー銭湯とか、様々な浴槽やサービスのあるゴージャスな温泉が増えてきているんです。ぼくは、非常に少なくなっている昔ながらの銭湯を会場にしようと考えました。
音楽家としての興味では、お湯のパシャパシャとかドッボーンという音が面白くて、お風呂で音楽会がしたいと思ったのです。また、銭湯はタイル張りなので、音がよく響くので、歌が歌いたくなるのですが、普段は許されないので、合唱もしてみたいと思いつきました。この二つのアイディアに、福岡アジア美術館の交流係の中尾智路学芸員が共感してくれ、プロジェクトが立ち上がりました。
アジア美術館の学芸課は、非常にユニークで、展示・収集係と交流係の2つの部署に分かれています。交流係はワークショップや滞在制作など、アーティストがいろんな人と交流するプログラムを運営することが主になっている係です。せっかく「交流係」ですから、積極的に交流の要素を増やそうと、お風呂で一緒に演奏したい人を募集して音楽会を組み立てようと考えました。
最初は、五線の楽譜に作曲して、混声合唱の経験者で合唱をするつもりでしたが、実際に募集してみると、合唱経験者は、お風呂で歌いたい人が少ないのか、合唱の経験が少ない方が多かったので、方針を変更しました。それで、リハーサルは合唱曲を作曲するワークショップになり、合唱する歌詞をダジャレで考えたりして「グローリア・インエクセルシス、デオー」というラテン語をもじって、「風呂屋ー、いいね癖になる、よー」と歌っています。
お客さんには男湯と女湯の脱衣所に入ってもらいました。銭湯の面白いところは、男湯女湯それぞれの脱衣所から、反対側の浴場の音は聴こえるが姿は全然見えないのです。だから僕は通路を行ったり来たりしながら、どちらの脱衣所のお客さんにも姿が見えるようにパフォーマンスしました。お風呂なので本来は水着は着用しないんですけど、学芸員の中尾さんと相談する中、一般公募で参加する人を集める上でハードルを下げ、今回は水着着用でやろう、ということになりました。ちなみに普段は40度くらいのお湯ですけど、それだと長時間入っていられないので、この日は36度ぐらいに温度を下げてもらいました。
この「大春湯」という福岡市内にある銭湯なんですけれども、この日は、アートに関わっている人や批評家や新聞記者とか含めて、本当にいろんな人も来ていました。ですが大春湯の女将さんはそういう人たちからの反響にはあまり関心がなく、この日来ていた福岡市浴場協会という銭湯の組合の人の反応を気にされていたそうです。その人が「あぁ、今日はとても良かった」って言ってくれたそうで、心底やって良かったとコメントされたと聞きました。イベントの成功やアートの価値は人によって本当に全然違うのですが、この女将さんの尺度にとっての成功と、ぼくにとっての成功が一致して、良かったです。もしその銭湯協会の人が駄目って言ったら、他の全部の人が良いって言っても多分銭湯の女将さんにとっては、失敗かもしれないんですね。でも、後から聞いた話だと、銭湯の女将さんがこの演奏会が進むにつれてどんどん楽しくなってきて、最後は番台の上に立ち上がって乗り出して見ていたのだそうです。
パフォーマンスの空間としては、視覚的には半分しか見えないけど、聴覚的には全ての音が聴こえるということです。半分しかお客さんに見えないという状況の演劇や音楽は初経験で面白かったです。だったら、逆に劇場空間などでも、敢えて音は聞こえるけれども見えない、という場を設定するのも面白いかもしれません。お客さんが入場する時は男湯女湯どっち側に入っていただいても良いというかたちにしていたんですが、普段は女湯に入れないから男だから女湯の側から見ようとかいう人とか、なんかやっぱり女だから女湯に行こうとか、お客さんはいろいろなことを思いながら場所を選んでいましたね。
ちなみに、2010年8月28日には、「あいちトリエンナーレ2010」の委嘱で『プールの音楽会』を開催する予定でいます。

「お湯の音楽会」DVD (09)
02 『ズーラシアの音楽』
野村誠:『横浜トリエンナーレ2005』で、野村幸弘さんと恊働でいくつかの映像作品を出したんですけれども、その中に『ズーラシアの音楽』というのがあります。横浜にズーラシアという動物園があって、行かれたことがある方もいるかと思うんですが、その動物園の動物と僕が共演するという映像作品です。実際に、アリクイがぼくの鍵盤ハーモニカを鼻で演奏したりします。よく絵本なんかだと動物が音楽を奏でだしたとか、演奏しながら踊りだすとか、そういうような記述があります。児童文学の世界では動物が音楽をすることが頻繁に出てきます。しかし、実際に動物と共演しようと思っても、上手くいかないこともいっぱいありまして、そういうことに随分昔から僕は気になっていて模索してきたんです。そして動物園の飼育係の人、いまは飼育係ではなくてズーラシア教育普及担当の長倉かすみさんという方がいます。その人はズーラシアに就職する前にイギリスやフランスなど、ヨーロッパのいろんな国の動物園を一年間に80園ぐらい回り、ボランティアとして働くということを、奨学金をとってやっていた方で、教育プログラムを学ぶためにボランティア活動をし続けた上で、ズーラシアに就職したという、非常に面白い方です。横浜トリエンナーレにちょうど作品を出す機会があったので、是非ズーラシアで作品を作りたいなと思って作ったものが『ズーラシア音楽』です。これには10種類の動物が出てきます。
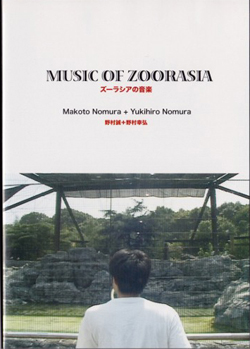
「ズーラシアの音楽」DVD (05)
03 『ズーラシアの音楽』のきっかけ
野村誠:特にクラシック音楽のコンサートになると、未就学児入場お断りということが多いですよね。音楽会の側からすると、とにかく予想できない雑音は出さないで欲しいという発想があるので、静かに聞ける人しか入っちゃいけませんってなるわけです。でもその一方で、参加型音楽会のように"お客さん、ぜひ一緒にご参加下さい"みたいな場合もあって、偶発的に何か音が出てもいいですよ、という話もあるわけです。では、音楽会にはどうして動物は来ちゃいけないのか、と考えるようになって。もちろん来ちゃいけないとは書いてないんですけど。動物入場お断りとかってコンサートホールにはたぶん書いてないですが、NHK交響楽団定期演奏会にペットを連れていくことはたぶん出来ないですよね。つまり、不確定要素を徹底的に排除するか、それとも不確定要素を喜んで自分の作品の中に内在させるか、ということです。どちらの立場もあると思いますが、後者の立場を取るのならば、不確定要素は、できるだけ予測不能である方が面白いと、ぼくは思います。その点で、動物達とのセッションは、非常に刺激的でした。
それと、音楽会をどんな場所でするかということ。
"音楽"と"場所"には密接な関わりがあると思うんです。銭湯で行う音楽会と、動物園で行う音楽会は、同じプログラムの音楽会にはならないですよね。それはたぶん美術作品でも同じだと思います。そして、それとは逆に"場所の特性を極力殺してしまう場所"というのがありますよね。例えば美術館のように、わざと壁を白くして何の特性も持たせないようにしたり。他にも、ダンスや演劇を行うような劇場になると、暗転した時に真っ暗になるように壁を黒くしていたりします。コンサートホールなら残響を残すように、音が響くよう木の壁だったり、コンクリートの壁だったりします。この講義室も壁に穴を空けて響きを吸収するようにし、言葉を聞き取りやすく無駄な反響がないようにしてあります。
しかし、こういう場所では、"場所から受けるインスピレーション"が非常に乏しいです。僕だったら、こういうぶつぶつの穴の単純な模様の場所で演奏するよりは、いろいろな場所に出向いていって、場所からインスピレーションを受けて何かをやりたいなって思うんです。

「ズーラシアの音楽」(05) DVDの映像の一部
04 アイコンギャラリーでのパフォーマンス
野村誠:実際に先ほど言った動物が来てもいい音楽会というのを、イギリスのバーミンガムにあるアイコンギャラリーで開催しました。お客さんの中には、インコやハムスターなどのペットを連れてきてくれた人がいて、実際に、犬がカメに強い興味を示し、吠え続け、その鳴き声に合わせてぼくが鍵盤ハーモニカを演奏しました。この音楽会は、アイコンギャラリーの「パフォーマンスウィークエンド」というフェスティバルの一環で開催しました。「パフォーマンスウィークエンド」の時期には、いろいろなパフォーマンスアーティストが次々とパフォーマンスを繰り広げていて、僕のパフォーマンスはその一コマです。

『動物との音楽』の中の「ペットとの音楽」DVD (04)
05 自身について、そして作曲
野村誠:僕は紹介にもあるように、芸術大学には行っていません。この場には高校生の方も多いと思うので、少し僕自身について話したいと思います。高校一年生の終わりの時に、僕は愛知県出身で当時名古屋に住んでいたんですけれど、やっぱり芸術大学とかに行って作曲を勉強したほうがいいのではないかと思いました。それで当時、名古屋に住んでいた戸島美喜夫さんという作曲家に相談させてもらいに行ったんです。彼は作曲家で「グループ音楽」という即興音楽のグループのメンバーでもあった人です。「グループ音楽」には小杉武久さんとか塩見允枝子さんとか、後に「フルクサス(fluxus)」と呼ばれる、1950年代から60年代にニューヨークで即興やパフォーマンスなどの前衛的な活動をされる方々もいました。
戸島美喜夫さんを尋ねて行った時、何と言っても僕は高校生だったので「僕が教えてあげるようにすれば君の才能は開花するよ」なんて言ってもらって、レッスンを受けることができることを、期待していました。しかし、先生はそんな僕に2つのことを言いました。ひとつは、「これは君の作品というよりは演奏だね」と言うこと。僕は高校生の時全然意味が分かりませんでした。作品というよりは演奏というのは、どういうことなんだろうと思った。もうひとつは「作曲の学生は、先生にここは直せと言われたところを直しているようでは一流にはなれない」と言うこと。僕は、音大受験に必要な和声学とか対位法とか、そういうテクニックを身につけるためにレッスンを受けようと思っていました。しかし先生は「直せと言われたことを直していたら一流にはなれない」と言ったのです。それで僕は高校生ながらに「直せと言われたところを直していたら一流になれない。しかし先生に直せと言われたところを直さなければ、音大の入試には受からない。つまり、音楽大学に入っても一流にはなれないのでは?」と考えたのです。そして、自分で考えてやる、もしくは一流になるのは諦めて先生に習う、どっちにしようかと考えたんですね。そして、僕は自分で勉強する道を選んで、音楽大学ではないところに行きながら、自分なりの音楽を志しました。
06 作曲における不安定な要素について
野村誠:音楽は誰かが演奏しないと音になりませんが、作曲は演奏してください、と他人に預けることができます。しかし、音楽大学に行かないという選択をした僕は、難しい曲を作っても演奏できる人が周りにほんの少ししかいない、という状況でした。つまり、曲を作ってもその通りに演奏できない、ということです。そこで僕は逆転の発想をして、僕が作った曲をその通り演奏できない人たちと演奏するのは、もしかしたら面白いんじゃないかと考え直しました。つまり、これを弾いてくださいと僕が言って、みんながドレミファソ、と演奏した時、それは僕が作った曲が僕のプランした通りに演奏された、ということなります。けれど、ドレミファソ、がドレファミソなってしまったり、ドレラソファになってしまったり、その通り演奏できないということは、逆に予想できない新しい要素を組み込んでくれるのではないか、と思ったんです。そして、それに対して僕が、面白いとか面白くないとか、そういうやり取りをしながら音楽を作っていくことが出来る、ということに気づきました。学生時代の僕はそれがどんどん面白くなってしまって、子供と一緒に音楽を作ってみたらどうだろうとか、いろいろなことを考えました。
07 老人ホームでの共同作曲『セッション』『大正琴リミックス』『たどたどピアノ組曲』
野村誠:そういう学生時代を経て、コンサートや展覧会をやっていても、お年寄りの人と遭遇する機会がすごく少ないことに気づいたんです。なので、実際に老人ホームに出向いて、音楽を作ってみようと思いました。このプロジェクトでは、お年寄りの方の演奏をビデオで撮影して(映像:上田謙太郎)、コンサートの作品の素材にしました。お年寄りの演奏の中には不安定なフレーズや不規則なリズムが多くあります。それは、ある見方から言えば、不正確ということになると思うのですが、ぼくに言わせれば非常に複雑な表現なのです。その複雑さに向き合ってみようという挑戦を、ぼくはしようと思って、この作品を作りました。この複雑さをそのまま把握できる鑑賞能力が僕に十分あればいいんですが、複雑すぎて、法則性がつかめません。そこで、短いフレーズをループさせる手法を使い、不規則なフレーズを何度も反復させることによって規則性を見出すことにしました。僕がいいなと思った場面をより選って編集しているので、凝縮されたお年寄りの複雑な演奏に合わせて、ぼくは演奏しなければいけません。これは、僕にとって試練で、非常に勉強になりました。
08 先駆的な取り組みについて
岡部あおみ:私が野村さんの作品を初めて見たのは、パリの国立高等学校で行われた日本の現代美術の展覧会「Donai yanen!」でした。私と野村さんは美術館を介して会うことが多かったんですね。野村さんはご老人とのコラボレーションで作曲していく活動を、10年ぐらい前からやってらっしゃいます。いまようやく、美術の分野でも老人ホームの方々とか子供たちとのワークショップが盛んになってきていますが、野村さんはそれ以前の早い時期から活動されていて、以前からとても興味を持っていました。
『ズーラシアの音楽』でも、テレビで見る動物番組などは後から音楽を付けているのに対して、野村さんの作品では私達が聞いている音楽を、動物も一緒に聞いているんですよね。
野村誠:僕もライオンとか、あんなに聞くと思わなかったです。実際に撮影した時には、20分も30分も1回あくびをした以外、ずーっとこっちを見ていました。撮影の後、ライオンってああいうものかなあと思ってベンチで休んでいたら、子供が来てライオンにちょっかいを出すと、ものすごい勢いで吠えるんですよ。クラシックコンサートをおとなしく聴いていた人が家に帰って子供をものすごい勢いで叱りつけているような感じですね。 岡部あおみ:動物が音楽を聴いてどんな反応するのか、『ズーラシア音楽』のような音楽会をさせてもらえる機会はほとんどないと思うので、とても興味深かったです。最後の場面ではピアノを弾かれていましたが、主に、楽器は鍵盤ハーモニカを使っていましたよね。
09 鍵盤ハーモニカについて
岡部あおみ:鍵盤ハーモニカは10年ぐらい前に発明された楽器らしいですよね。学生のみなさんは見る機会は少ないと思うんですけれども。
野村誠:いえ、学生のみなさんは、ほぼ100%の確率で鍵盤ハーモニカをいままでの学校教育の中で演奏したことがあるはずです。鍵盤ハーモニカ自体が発明されたのは1959年のドイツで、もとは輸入品でなんですけど。最初は、鍵盤ではなく白鍵側のボタンと黒鍵側のボタンを押さえて吹く、おもちゃのような楽器でした。それに日本の楽器会社が手を加え、小学校の音楽で当時取り扱っていたハーモニカと足踏みオルガンを一台でできる画期的な楽器、ということで売り込み、普及させたんです。だから、海外では珍しい楽器なのであまり見ませんね。評価が定まった楽器ではなく、歴史が浅い上に、教育用の玩具的な楽器と見なされているので、この楽器の本格的な演奏を追求しようと考えました。この楽器のオーケストラを結成したり、この楽器のための作品を多くの作曲家に書いてもらったりしています。昨年は、ロンドンで鍵盤ハーモニカに関するレクチャーコンサートなどもしましたし、一昨年はベルリンで鍵盤ハーモニカに特化した演奏会を開催しましたが、現地の人の反響が凄かったです。21世紀の日本の音楽と言ってもいいと思うのです。
10 北斎と木琴
岡部あおみ:最近ですが、野村さんの北斎というテーマでされたコンサート演奏を拝見する機会がありました。今日も草履を履かれているので、そのコンサートからの流れかなと、思ったんですけれども。木琴を作るというのがとても面白かったです。北斎の作品に演奏の場面があって、そこに出て来る楽器のひとつが木琴なんですよね。
野村誠:21世紀の日本で鍵盤ハーモニカがあるように、江戸時代に、珍しい楽器があったわけです。そのことに気づかせてくれたのが、北斎です。北斎は北斎漫画という当時のイラスト集みたいなもの中で、いろんな生活の場面を簡単なタッチで描いています。僕は、その中に不思議な四重奏の絵を見つけました。
ひとりはお琴のような楽器を弾いている。もちろん江戸時代にお琴を弾いている人がいてもおかしくはない。ひとりは尺八を吹いている。もちろん尺八があっても全然不思議じゃない。胡弓を弾いている人もいる。けれど、そこに混じって、バチを振り上げて木琴を演奏している人が描かれていて。それを見た時、江戸時代に木琴があったのかと驚きました。邦楽の世界で、木琴の奏者など聞いたことがなかったからです。
また、その木琴はインドネシアのガムラン音楽に出てくるガンバンという楽器に非常によく似ているんです。江戸時代に、日本にインドネシアの音楽が伝来していたのだろうか?それで、江戸時代の浮世絵を調べていくと、江戸時代にも木琴がブームだったらしいのです。しかも、その木琴の形状はインドネシアの物に似ているが、断然、小型で、一体、どんな音がしたのだろうと、自分なりに作ってみたいと思ったのです。
実際に調べていくと1804年に天竺徳兵衛韓噺という歌舞伎が上映され、それが東海道四谷怪談で有名になった演出家の鶴屋南北のつくった出世作なんです。その天竺徳兵衛韓噺の話が変なんです。要はお化け屋敷に泥棒みたいに忍び込む話なのです。その忍び込むときに天竺徳兵衛は越後座頭という視覚障害の人になりすましてお屋敷に忍び込むんです。座頭とは按摩をしたり楽器を演奏したりというような職業に就くことが多い人のことです。そして普通は三味線などの楽器を持って行くんですが、天竺徳兵衛は「私は越後座頭の者です」と言って木琴を背負い泥棒に入ろうとするんですね。ところがそれは怪しいので「お前何者だ」と聞かれると「私は怪しい者ではありません。木琴の演奏家です。」と言い、木琴をたたきながら越後節を歌うという話なんです。そしてその当時の人気俳優が木琴をたたきながら越後節を歌うのですが、やはり怪しいと言われ慌てて池に飛び込み、そこで場面が展開する、というシーンで出てきたらしいんです。すごく面白いですよね。なんで木琴を背負って忍び込んで、怪しいじゃないかって思うんですけど。(笑)でもそういったことを調査し再現することで、当時の音楽ってどんなのかなと想像して、そこから僕がまたインスピレーションを得て新しいものをつくっていくんです。
岡部あおみ:最初に『お湯の音楽会』がありましたが、日本で行われたアンケートで、一番のストレス解消法は圧倒的に音楽を聴くことだそうです。でも最近の日本人はアイホーンやiPodで聴くことが多いように思います。野村さんはいわゆる通常の聴き方ではない、音に対する人々の身体的、意識的、認識的な関わりのすべてを変えてみたいという試みをされていて、人に広がりを持たせて開放させてくれるようなところがありますね。『お湯の音楽会』に参加した人は既成概念が思いっきり開放されたんじゃないかと。やはり最初に出会った人がグループ音楽の方だったところから、そうした斬新なアプローチがずっと続いてきているのかなとも思います。もちろんご自分でいろいろ考えながら、常に自分にとって何が正しいのかを模索しつつやってこられたのだと思いますが。
野村誠:そうですね。今会場に高校生がどれぐらいいるのかわかりませんが、ひとつの知識を効率よく学ぶために先生に教わることはすごくいいことです。ある分野についてものすごく詳しく知っている人たちが「それだったらこの本読んだらいいよ」「これ見に行ったらいいよ」と教えてくれるので、学びたいことにダイレクトにアクセスできるんですね。
でも逆に僕はものすごく効率の悪い道を選んでしまいました。あの時僕が「君はこういう風に勉強したらきっと成長するから僕についてきなさい。」と言われたら、僕はそう思い、違う自分を展開していたかもしれないです。でも逆に言うと効率よく教えてくれる人がいないために、僕は無駄なことをいっぱいしながら学ぶしかなかったんですね。例えば「この本を読めばいいよ」と先生が紹介すればすむ一冊に辿り着くために十冊や二十冊読まなければいけなかったり、その音楽を聴けばいい、というのにたどり着くまでに聴かなくてもいいものもいっぱい聴く羽目にもなるし、やらなくてもいいことをいっぱいやったと思うんです。そういうことは無駄だったのかもしれませんし、無駄じゃなかったのかもしれませんが、そういう遠回りをしながら一歩一歩身につけ、勉強したのだと思います。

「野村誠×北斎」(10)
(C)松本和幸 アサヒ・アートスクエアにて
11 アジアと音楽
岡部あおみ:さきほどのアイコンギャラリーもそうですが、イギリスでの活動がよくありますね。
野村誠:僕はイギリスに一年住んだことがあって、イギリスはけっこう行っています。イギリスは、音楽教育やコミュニティ・ミュージックが盛んで、そういったシーンの活動にも興味を持ったのですが、世界観を変えてしまうような作品には、なかなか出会わない。そんな中で、ヒュー・ナンキヴェルという作曲家が、地方都市で地元の子どもや家族を集めて、即興や聴くことをベースに非常にユニークな音楽を生み出していて、彼と一緒に作品を作りたいと思いました。2004年からヒューと開始した「ホエールトーン・オペラ」は、オペラという名前ですが、実験的で即興的で越境的で柔軟性の高い自由なオペラです。
岡部あおみ:アジアとの関わりはいかがしょう?
野村誠:さっきの北斎にも通じることですね。大阪で、インドネシアのガムランを演奏しているダルマブダヤというグループから、インドネシアでコンサートツアーをするための作品を作ってほしいと委嘱を受けたのがきっかけでインドネシアはもう何度も行っています。ガムランの作品もたくさん作っています。そして、インドネシアの現代ガムランシーンの中には、非常に面白い音楽家がいます。しかし、こうしたアジアの情報は現地に行かないと、なかなか分からない。出かけてみると本当に面白い人がいっぱいいるので、個人的に調査しに行かなければいけないと思いました。それで、映像の野村幸弘さん、民族音楽学の中川真さん、ジャワ舞踊の佐久間新さんらと、i-picnicというプロジェクトを立ち上げました。まだアジアの国ではタイとインドネシアとカンボジアしか行ってないんですが(イタリア、オーストリア、ハンガリーにも行きましたが)、行く先で、本当に面白い出会いがあります。そこで出会った人たちとその場の出会いの即興演奏を映像でドキュメントしています。多分それをやることでネットワークが広がると思うんです。きっと本当に面白い人がまだ知らないところにいると思うし。
岡部あおみ:そうですね。日本で知られていない音楽もたくさんあって、私もたとえばバングラデシュの吟遊詩人の音楽を最近知りました。
野村誠:バンコクのアナン・ナルコンという人がコーファイというタイの伝統音楽、日本で言えば雅楽にあたるような、伝統音楽のグループをやっています。テクニックがすごいだけじゃなく、実験的なことや伝統音楽にのせて自分たちでラップをやったり、エレクトロニクスと一緒にやったり、面白いことは貪欲に何でもするんですよね。映画音楽も作るし、本当に面白い。でもぜんぜん情報が入ってこないんです。彼にもi-picnicに参加してもらい、一緒にオーストリアのフェスティバルに参加したり、エディンバラ大学で一緒にワークショップをしたりして、コラボレーションを開始しています。また、今年の秋からインドネシアに一年住み、現地の音楽家とプロジェクトを開始する予定です。
12 現在の野村誠の興味
岡部あおみ:野村さんご自身、今こういうことを一番やりたいというような願望というか、思いのようなものはあるのでしょうか。これまでの活動はすべてに独自性がありますが、基本的に招待されたりしたときの場や機会、展覧会などの内容によって、オファーされる度に新たに考えて、こうした場ならこれをやってみようかなと決めることが多いと思うのですが、こうした他者からの条件を抜いて、ご自分でこうしたことをやりたいという何かがあれば。
野村誠:これが一番やりたいと言うのは難しいですね。(笑)やりたいことはいっぱいあるので。
野村誠を一人のアーティストととらえると、難しいです。鍵盤ハーモニカ奏者としての野村誠は、鍵盤ハーモニカの世界を極めようとしていますが、作曲家としての野村誠は、オーケストラの傑作を書こうとしています。しかし、子どもと音楽を作る野村誠は、子ども達と音楽の実験を繰り返し、音楽の常識を根底から覆したいと考えています。理論派の野村誠は、独自の音楽理論を提唱しようとしています。アジアに出かけて即興を繰り広げる野村誠がいて、イギリスで活動する野村誠がいます。複数の野村誠を併存させることは、商業的に言えば、非常に効率が悪い。野村誠というイメージを固定化させて、その路線でターゲットを絞り、売り込みをかけて、売っていけばいいわけですから。しかし、ぼくは、そうした複数の野村誠を共存させながら、多面的に音楽の探求を続けていきたいと考えています。そして、その一つ一つが、およそ繋がりそうにない別々な音楽性に見えても、それが、相互作用して浮かび上がる音楽が提示できる、と考えています。ですから、目指しているところは、この複数の野村誠によるコラボレーションをどう実現するか、です。それを実現するために、この複数の野村誠を収束させることがなく発散させていく。今は、そういう段階だと思っています。
今日ここにきたことは、ここの世界の方々とあんまり話をしたことがないので、そういう点、また僕が持っている感性とは違う発想や考え方を持っていて、違うバックグラウンドを歩んでこられていると思うんで、いってみればまた一緒に何かをする機会や交換できればすごく楽しみです。
岡部あおみ:今回参加した学生たちがレクチャーの後で、意見や感想を書いてますので、後で読んでいただければと思います。
13 ゆとり世代の音楽とアート
野村誠:ひとつ気になっていることで、たぶん今の大学生ぐらいの人からゆとり教育が始まった世代ですが、失敗だった、学力重視と言われたという話を聞いているんです。それはなにをもって失敗だったのか知らないんですけど、逆にゆとり教育世代で育ってきたひとたちは、これから活躍すると思うんです。逆にいうと僕の世代は競争を強いられるような小、中、高等学校時代でした。でもそれは違うなと思ってアート方面の方はアートをやっているけれど、僕らの世代のほとんどが競争というものが体のなかに染みこんでいて、いくら儲けるか、あそこのなによりもこっちが勝ち負けというのをずっとやり続けてきた。そのときにゆとり教育というのはどういうことをやってきたのかは知らないけど、ひょっとしたらそうじゃない面も僕らよりは多かったかもしれない。社会の状況も違うし。でもそういうふうに育った人たちの中からどんなアートが出てくるのか、どういう価値観があるのか、そういうことはすごく聞いてみたいと思うし、注目しています。
14 音大と美大
岡部あおみ:武蔵野美術大学に音楽学科はありませんが音楽が大好きで実際に自分で作曲や演奏をしている学生はかなり多く、街中のクラブでDJをバイトでやっている人もいます。そういう意味では音楽との関わりが広がっている気がします。本当は音楽の道に進もうと思い、音大を受けようか迷って、結局ビジュアルアートを選び、美大に来た人もいます。今は両方できる人が増えていると思いますが、逆に音大に入った人で、現代アートやビジュアルアートが好きな人がどのくらいいるのかは分かりません。
野村誠:音大に行っている人で現代アートが好きな人は少ないと思いますよ。
岡部あおみ:美大に来ることをチョイスした人は、守備範囲が広い人が多いですね。
野村誠:音楽大学へ行った人は、何であんなになっちゃうんでしょうね。高校生の時に自分が音楽大学を進学しない選択をしたことは正解だったかなとは思っています。
岡部あおみ:将来、演奏家として独立したり交響楽団で演奏したり、ピアノの先生になることを決めている人は技術を徹底的に学び、実技経験を豊かに持つことが必要です。しかし、別の角度から社会に関わり、芸術のあり方をもう少し広く、新たな形で考えていきたいという考えで、音楽を一つの方法論として展開していく人が多くなっていますね。野村さんの弟子が増えているということかもしれません。
野村誠:武蔵野美術大学の近くに音楽大学があるのですか。
岡部あおみ:国立音楽大学が近いですが、音大系と美大系の学生は違うかもしれないです。
野村誠:ぜんぜん違いますよね。服装を見るだけで違います。
岡部あおみ:リラックスしている方が美大で、きちんとしている方が音大ですか。会場の方々でなにか質問はありますでしょうか?
質問者:武蔵野美術大学と国立音楽大学は、TACで提携しているので、国立音楽大学の授業を受けることができます。
野村誠:国立音楽大学の学生も、武蔵野美術大学の授業が受けられるんですね。
15 サウンドスケープデザインについて
質問者:現在はそういうシステムになっています。質問ですが、武蔵野美術大学はデザイン科がいくつかありますが、サウンドスケープというデザインの領域を専門に教える学科は特にないです。デザインという領域に音楽を材料として、どのようなことができるか何か考えていらっしゃいますか。
野村誠:サウンドスケープデザインについて僕もいろいろ思うところがあります。最近、旭川の街中を歩いていたら、20mごとに一つずつスピーカーが設置されていたときのことです。全てのスピーカーから、朝の8、9時ぐらいから夕方6時まで、旭川のお店の宣伝などを流し続けているのです。ぼくは、静寂を求めて、別の通りに逃げても、そっちでも流れていて逃げ場がないんです。そのとき、この中で暮らしていたら感性がおかしくなるのではと思いました。
またJRの駅などで曲が流れていますが、すごい音量で音楽を聞かせられます。しかし音は無視することができないですよ。そうした音を遮断しようと、ヘッドフォンをして音楽を聴く人が出てくる。それで今度は、そういう人に聞こえるように構内アナウンスの音量が上がって、電車のプラットホームや車内に耳に痛い音量できついアナウンスがかかります。同じアナウンスにしてもどんなスピーカーを使うとか、どういう目的でどんな音質で聞こえたいか、音の専門家がいればもう少しデザインできると思います。あの音にしてももっとやりようがあるかなと思います。
今はサウンドスケープデザインをやっている人がどうなのかわかりませんが、基本的に音をどんどん足していますよね。聞こえなくなるからさらに新しくきつい音を足していき、どんどん音が増えていく。でもやらなければいけないことは、音をもっとスッキリさせることだと思うのです。無駄な音を減らし、必要最低限だけ残す。そして音質にもっとこだわった方がいいと強く思っています。スピーカーにしても聴き比べれば明らかにどちらかわかることでも、ミスチルが買っているからこれなのかなとか、業者に言われたからこれにしただで、決めてしまったりする。例えば大学の講義室に入れるスピーカーにしても同じことかもしれない。同じ講義でも先生が無理して力説しなくても伝わりやすくなるかもしれない。そういうことのような気がしますが、そういうことに何かを言える耳のいい専門家が少ないですね。
サウンドスケープという言葉自体はカナダのマリー・シェーファーが騒音問題を取り扱った際に生まれた言葉です。騒音だけではなく、あらゆる環境音を取り扱うために生まれた概念です。世界の音自体をオーケストラが演奏しているみたいだと言い、音の風景を研究するプロジェクトを始めたことがきっかけです。音の風景があることに、デザインの概念を持ち込みサウンドスケープデザインという言葉ができたわけですよね。ですので本来、騒音問題について考えることからスタートしてサウンドスケープ、サウンドスケープデザインと展開した時代背景があるわけです。音を足すことで人々がもっと音について繊細になり、耳を澄ますようになっていく、という意図なのでしょうが、音を必要以上に足しているケースが非常に多い。確かに音を抜く作業は、仕事をしたという感じにはなりにくいんですよね。音を足すと、私が足したと言えるけど、抜いたっていうのは主張できないと思うんです。だから、サウンドスケープデザイナーは、音を足す。しかし、音を抜いていくことこそ、センスが要る。すごく大切なことなのです。
岡部あおみ:2010年に卒業したゼミ生で、サウンドスケープについての卒論を書いた人がいます。何気ない音に耳を澄ますきっかけをもつこと、日常の時間の中で音を意識できるようなデザインをしていくのがいいのではないかという結論を出していました。また現在のアーティストと音との関係に、歴史的にはどのような繋がりが見られるのか、未来派やジョン・ケージを含めて検証しています。ご関心があるようでしたら、読んで見てください。ではそろそろ時間ですので、野村さん、興味深いレクチャー、ありがとうございました。
