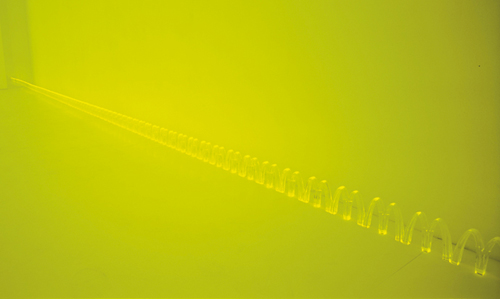インタヴュー
中村政人×岡部あおみ
学生:浦野直子、笠原左知子、國井万紗子、鈴木さやか
日時:2000年5月12日
場所:SCAI THE BATHHOUSE
岡部あおみ:まず最初に、コマンドNとアーティストランスペースなどについてのお話を伺えますか。東京にはスタジオ食堂もありましたが。
中村政人:アーティストランスペースとは、スペースに依存していますが、アーティストイニシアティブや、ロッテルダムなんかだとキュレータ−ズイニシアティブがあり、誰が主導権を持ってアートを始めるのか、アーティストが主導で始める場合と、キュレーターが主導を持って始めたり、それらをミックスして始めたり、または、公のお金でやるのか、民間のお金でやるのか、制度となっている美術館で始めるのか、色々なイニシアティブの在り方としてヴァリエーションがあると思うんですね。
日本での特徴的な要因は貸し画廊です。貸し画廊制度が60年代から70年代にかけて神田を中心として発達したんですが、なぜ重要かというと、日本では、アーティストが自分で考えて、自分で行動を起こして、何か自分で見せる、というアーティストがイニシアティブをとった行動が、実は貸し画廊から広がってきたと思えるからです。もちろんその前の50年代後半からのアンデパンダン展であるとか、戦前のそれぞれの作家レベルでの動きは、ある程度公募展に回収されてしまう要素が強い。本当の意味で自主的に動いてきたのが60年代70年代で、作家がお金を払って場所を借りて、自分でDMも作って、搬入・搬出もして、人が来たら全部自分で作品の説明もして、売買も場合によって作家が、お客さんとか友達を相手にする。アーティストがオールマイティーな活動をしていた。それがすごく日本的というか、欧米ではまず考えられないことですね。作家は作品を作り、作品を見せる人は画廊の人だとか美術館の人達で、作品に対して敬意を払って、「おもしろいから」、「文化的に価値があるから見せましょう」というのが通常で、日本の場合はそういう意味では、アートの在り方が表層的な形式として入ってきていて、実体のエモーショナルな行動であるとか、内在する精神性とか、そういうものを含めて入ってきてなく、ずれてしまったという部分がある。そういう意味も考えると、現代美術の展示が貸し画廊で行われてきた60年代70年代がすごく重要な動きだったと思う。アーティストが主体的に何かを導こうと、しっかりと実感をともなった現場がそこにはあったという意味でです。
岡部:最近企画画廊が増えて、貸し画廊に対しては、ネガティブな認識も多くなってきましたね。でも、アーティストの立場から見れば、展示の機会やスペースとして、それをどう活用していくかが重要で、ひとつの自主的な活動であったと言えるということですね。
中村:そうですね。そこが良い部分・悪い部分があるのだけれども、良い部分は、最初に言ったように主体性がある。悪い部分は、それが貸し画廊という制度になってしまったという部分が80年代以降に出てくる。つまり制度になってしまうとそれが美術だという思い込みが出てしまうわけです。貸し画廊を借りて展覧会をすることが、そのレールの中でのひとつのポジションになってしまう。学生でも、誰でもお金を払えば展覧会が出来て、お金を払えば作品を見せられて、作品が見せられれば、それがあたかも作品のように見える。で、作品を発表してる人はあたかも作家のように問われる。それは、初めて大学入った子でもできるわけです。何十年と作品を作っている人でも同じ条件なわけです。アートとは何かという大きなクエスチョンがその中では消えてしまっているのが問題です。だから80年代以降になってくるとコマーシャルギャラリーがどんどん増えて、今おっしゃったようにアーティストの主体性だけではない側面、他の人の仕事、例えばディーラーか、ギャラリストとかの言葉の使い分けの問題も出てくる。
岡部:日本ではディーラーとギャラリストとをどう使い分けているのですか?
中村:日本流に、スペースを持ってることと、スペースを持っていなくてもディーリングだけで仕事ができるってことで、少し区別をしてきたと思うんです。コマーシャルギャラリーの良さはちゃんと作品を売る力がある。売ってマーケットを育てていく力がある。作家とコレクター、作家と美術館を結び付けていく力もある。それは今までの貸し画廊には無かったことなんです。作家は自分の力の限界があって、せいぜい友人関係や知り合い、家族、親戚関係で止まってしまう。友達も1回目は買うけど、2回目からは難しい。親も一緒。要するに、広がらないマーケットですね。その中で、プロの人が出てきたのが90年代で、フジテレビギャラリーなど主要コマーシャル画廊で働いていた人達が、独立して画廊をはじめ出す。作家とは違う仕事の流れがはじまり、90年代以降面白くなってきている。
そして90年代も終わりになって、新しい世紀を迎える頃に、コマンドNが出てくるわけです。ここまでが前フリですが、要するに、アーティストが最初持っていた主導権は、一体どこにいったのかと。もしくは50年代、例えば赤瀬川源平さん達がハイ・レッド・センターで、ボンと町の中へ出ていったアヴァンギャルドな精神は一体どこに消えていってしまったのか。赤瀬川さんに僕がインタヴューした時に、「いやそれはね、アヴァンギャルドっていうのは市民化するんだ」って言ってたんですよ。例えば篠原有司男さんが、50年代後半にモヒカンにしてたわけです。で、それは当時ものすごいアヴァンギャルドだったわけだけど、今やそれはごく当たり前。流行として市民化していったわけですよ。市民化していくアヴァンギャルドほど悲しいものはないっていうか、精神だけがなくなって、ファッションだけが伝わるわけでしょ。ある意味で50年代の頃の作家の主導権というのは精神がどこかに行ってしまって、形式だけが伝えられてしまう。
日本を見渡すと各県に約一個ずつ美術館ができて、ものすごい美術館の数ですよね。民間企業も数多くメセナとしてのギャラりースペースやミュージアムを持っている。これほど美術館と美術関係のスペースが多い国ってそんなに無い。ものすごい数になってしまったと思う。でも果たして、作品、内容ですよね。作家がやってきたイニシアティブなまたはオルタナティブな精神が見られるのかといったなら、抜け殻しか見られない。どこに行っても印象派の絵だったり、評価の定まった作品と地元の作家の絵ばっかりだとか。ほぼ同じようなコレクションが美術館で並んでいる。そこで僕が思ったのは、コマンドNの考え方は、作家が主体的に何かを伝えることつまり、アーティストがイニシアティブを持ち社会に参加、介入する。そのイニシアティブの方法がアートという思考回路を通過してでてくる。やれといわれて始める事ではない、創造力の純粋性を大切にしたい。マッキントッシュにおいてですがコマンドキー+Nキーつまり「新規ページを開け」というスクリプト自体がコマンドNの基本的考え方なのです。
それがどういうことかというと、ひとつはやはり東京という街です。東京という街の中で、僕らは今生活をしていて、そこでメッセージを伝えようとしている。もちろんそれは、ひとつは東京に住んでいる人たちに。もうひとつは東京に来る人たちに。または東京からメッセージを外に向けて。あくまで東京っていう非常に限定されたローカルな空間に縛られているっていうことが大事。
もうひとつは、歴史の中でアートとは何かという、大きなもっと哲学的な意味を含めてだけれども、もう少し土地とは関係なくメタレベルで自分達にとって、この時代に生まれている中で、アートとは何かという大きなクエスチョンを見つけたいということがもうひとつある。ですから、欧米に対していわゆる共通言語となるアートという考え方と、地域において限定して成立するアート。つまりグローバルな視点でかつローカルならではの成立をめざしました。具体的には、秋葉原TVという企画です。

中村政人 「minimal selves」 2001
| 協力: | 株式会社am/pmジャパン、株式会社ファミリーマート、株式会社ローソン、
株式会社スリーエフ、株式会社セブンイレブン・ジャパン、
ジェイアール東日本コンビニエンス株式会社、株式会社ポプラ、
株式会社デイリーヤマザキ |
© Anne Hardy
中村:秋葉原TVは、秋葉原の電器屋街のテレビモニター、販売用のテレビモニターを一時的にジャックして、その期間だけ僕らの作った映像作品を流して下さいって言う企画です。音のメッセージを伝えたかったら、ラジカセにテープを入れて、プレイを押せば音が出る。売っているビデオデッキにビデオテープとカシャッと入れてプレイを押せば、映像が流れる。既存のハードをそのまま使用し、映像というソフトにおいて街の風景を変える。電機街振興会という秋葉原を管理している重要な組合があり、400店鋪以上会社が加入している。ラオックスも石丸電気も、サトームセンの社長さんも、全部加入している。その人たちがOKを出さないと、絶対それは不可能。次はお金をクリアしなくてはいけない。これは、同時ですけどね。私達はお金持っているわけではないので、プロジェクトを遂行するのに必要な寄付金を募らなくてはならない。アイディアを誰かに説明して、「こういうことが面白いわけですから」、「僕らこういうことを社会的にやるので、サポートをしてください」ということを始めたわけです。助成基金や芸術振興基金、国際交流基金、民間の企業メセナに対して、ファンドレージングしたわけです。なんステップかクリアしてやっとビデオテープをお店のデッキに入れてもらえることができる。東京の中でも秋葉原という限定した中でアートというメッセージを伝えようとした時に、立ち現れてくる壁を乗り越えようとすることによっておのずと地域の人たちとのコミュニケーションが派生してくる。その派生した要素がコマンドNの活動そのものになって行きます。あとプロジェクト単位で活動をするということもポイントですが。
岡部:コマンドNを立ち上げたのと、秋葉原TVを考えたのは、ほとんど同時なのですか?
中村:秋葉原TVが最初です。僕が秋葉原TVの企画を思いついた時に、一緒にやらないかとか、こういう考えでやりたいけど、事務所を秋葉原のそばにつくりたいんだということが始めです。
岡部:秋葉原TVを支えた運営とオーガナイズをした作家達が中心というわけで、作家が多いけれど、キュレーターもいましたね?
中村:メンバーの中でキュレーター人は、四方さんと阿部さんと堀さんの3人ですね。主に作家を推薦してもらったりしました。東京の今のアートシーンに、アーティスト主導型のスペースが無いためだし、例えば、小池さんがやっていた佐賀町だとかの先駆的な例はあって、非常にいい活動をしていたわけですが、アーティストや若いインディペンデントなキュレーターの人の生の声を、反映させられる場所がすくない。それはだんだん日本中で少しづつ増えてますよね。
岡部:増えてますね、最近。NPOという方向もあります。NPOの取得などが制度的に少し楽になったということもあり、確かに増えてます。
中村:同時多発的に増えているんです。やはり、今こういう時代だからこそ。
岡部:秋葉原TVの総予算はどのぐらいだったのですか?基本的にボランティアですよね。
中村:1回目が500万円ぐらいで、2回目が、予算案と実際に集まったお金は違うんですけれども、600万円ぐらいですね。人件費は0ですが。僕らの経費の出し方は、限界値を越えてる値段を探してくる。通常であれば100万円でなくては絶対できないという業者さんでも、「いや僕ら10万円しかありません」って。「残りの90万円どうするんですか?」と聞かれたら、「それは寄付して下さい」と目を見つめたりしてね(笑)。要するに、通常の人たちがやってるような動きではできないです。逆にいえばそれだけ僕らの能力がある。相手の人たちは普通の価格を出して普通の値段で仕事をとってくる。僕らはその差額90万円以上の能力があるわけですよ。1時間ですることを、10分でできる。その方が僕は魅力的。だからデザインやっても、デザイナーがやるよりもはるかにおもしろいものが簡単にできる。それがアーティストの面白さ。そういうネットワークを持ち、行動する実力がある。今は単に、社会貢献という言葉の中に埋もれてますが、行動に対してお金がちゃんと還元される作用があることなど、僕らのような活動が認知され、予算がもう少しつきやすくなることが望ましい。そのプロジェクトにより派生する様々な要素がアーティストの活動に付随しみえてくる。その付随し見えてくる要素こそ見えにくかった、感じにくかったものであり、その要素をさらに組み換え社会の中に還元させる。コマーシャルな始まり方だけで成立している活動は、その営利性ゆえに絶えずどこかで貯蓄されてしまい還元されない。
岡部:ご自分の活動及びアート等を思考するなかで、社会との関わりや還元性みたいなことを考え始めたのはいつごろからですか?昔からですか?
中村:どうなんだろう。例えば受験という中で社会との関わりを非常に閉鎖的には考えていたわけですよね。田舎から出てきて、受験するために予備校に行って、それこそそこで徹底的にしごかれて、それがひとつ社会との接点です。でも今度は美術の枠から一歩外に出ようとすると、勉強したことが全然役に立たない。ただ、今僕が考えているような意味で、志を持ったのは、韓国に行ってからですね。韓国に3年間留学した辺りから、ものすごく自分がやろうとしていることに対して、ひとつひとつ疑問を持つことと、自分がやってきたことに対しての影響、つまり教育を受けたことに対しての弊害を、自分のアイデンティティの構築・生成と共に、もう一度見てみる時間があった。「何で俺はデッサンがうまいのか?」とか、「おまえもうまいじゃないか」とか、韓国に行って、「それは石膏デッサンやってきたからだよね」とかいうのがハッキリ分かるんです。これはやってきてない子は出来ない。でも、本当の意味でのドローングがいいとか、うまいとか、面白いっていうのは別ですが、韓国でも日本でも、美大を出た人には、まあほとんどの人はまずデッサン力はあるわけです。100人いたら90人同じデッサンを描いてしまうという様な所に問題があるのではないかと思ったのが、韓国の学生と話していた時でした。
岡部:韓国に留学するきっかけは、中村さんご自身で選ばれたんですか?それとも大学の交換留学とか、向こうに受け入れ口があったためですか?
中村:真面目に話すと2時間かかるんだけれども(笑)。簡単に言うと、単純に自分の作家性。自分で選びました。日本政府の派遣と韓国政府が招待するのと2つあったんですけれども、韓国政府の招待の方で僕は受けたんですね。
岡部:その制度は今でも続いていますか?中村さん以後にも美術の留学生がいるのでしょうか?
中村:続いてはいますけど、美術は最初で最後でしょうね。
岡部:みんな希望しないのですか?
中村:韓国からはいっぱい来るけれども、そういう人達は陶芸だとか、東洋画ですね。多少前例はあるんですけれども、僕が行ったのは油絵科。油絵を勉強しに韓国へ行くようなやつはいないでしょ。
岡部:そうですねえ。
中村:油絵っていうよりもアートを勉強しに行くわけですよ。もう少し、広い意味で。ただそれは前例が無い。日本人としては最初で。まあその後1人も聞いたことがない。という日韓の関係なのでしょう。
岡部:中村さんの名前がすごく際立ったのは、韓国に留学された頃からでした。めずらしいなと思って。「ああ、新しいアーティストが出てきた」という気がしました。だいたい、みんなニューヨークへ行きたがりますから。
中村:まあそうでしょうね。僕自身もそういう意味ではそう言われることも多い。ただ、ニューヨークへ行くのは、後でいいと思った。ニューヨークって日本人のアーティスト予備軍って言われている人達がいっぱいいて、成功例として河原さんとかがいるけれども、層がもの凄く厚い。その中にまた同じカテゴライズとしてポンと入ることの魅力がそんなに無かった。と同時に、アメリカの消費文化のようなものにちょっと辟易していた。それだったら、キムチの方がおいしいなあなんて(笑)。韓国の伝統的な文化や美術に対してそれほど興味は無かった。
岡部:韓国のガールフレンドがいたのかなと思いました。
中村:いやいや、それはあとですよ(笑)。結果です。人生どうなるか分からない。
岡部:光州ビエンナーレなどに何度か行って驚かされるのは、最近韓国で現代アートの勢いが凄いことです。エネルギーにびっくりする。もちろん歴史的な背景で、近代美術に関しては研究もコレクションも植民地化とともに困難な状況に陥り、「私たちには現代しかないから」と韓国の方々に言われると、つらい気持ちで納得せざるを得ないわけなのですが。
中村:韓国の美術は現代美術ですからね。日本で美術って言った場合には、近代もあるし、いろいろな要素があるじゃないですか。現代美術っていったら全体の中ではすごく肩身が狭い。主流が現代美術っていうのは、その分シーンとしては豊かです。
岡部:そうですねえ。すごくやる気がある人が多いし、システムがだんだんでき始めてきている。まだ美術館は少ないですけれども。
中村:そうそう。ある意味では日本より全然進んでいるし、作品を楽しむ視点は韓国の国民性の方が豊かです。要するに、お金持ちの人達の幅がとても広いし、上は桁違いで、そういう人達は惜しみなく作品をサポートするし、買う。
岡部:それが日本の場合だと、財閥系のコレクションなどは戦前にはあったけれど、戦後になると企業にバトンタッチされた部分はあるにせよ、そういう意味での巨大コレクションは少なくなり、さまざまな方向に行っているように思えます。
中村:そうですねえ。でも良い方向に行っているのか、悪い方向に行っているのか。ただこういう方向には行ってほしくないというのはある。例えば簡単に言うと、「誰でもピカソ」とか。あのたけしの番組で、美術という言葉が使われて、浸透していく危機感は持ってます。非常にエンターテイメントな芸と、美術という言葉は違うと僕は思う。だから、その辺の危機感はきちんと言わないといけないし、態度で表現しなくてはいけないと思う。どうしても、わかりやすくっていうか、売れやすいものを売れやすいように作ることと、全く売れそうにないものを、作りたくて作っているのは質が違う話で、始めが違う話です。それが今、ぐちゃぐちゃになって、どっちでもいいよって、簡単に言う人も出てきている。ではそれなりにその考え方のヴィジョンがあるのかというと、そうではない。ただなんとなく、なだらかにジャンルが無くなってきたと言ってるだけで、次のヴィジョンに対する責任のある言葉ではないと思う。そういう意味でたけしのやっていることは、ヒエラルキーをひとつ構築する方法で、裾野の広げ方としては安易な広げ方だと思いますね。だから、一生懸命造作っていった人ほど馬鹿にされて、一瞬芸の人ほど20点貰えたりする。20点貰えて喜んでる作家も問題だし、それを見て「わあ〜」って言ってる吉本の芸人も問題だし、それをまたテレビでチャンネルを回して見てしまう僕らも問題だ(笑)、とは思うが、ついつい見てしまう(笑)。
岡部:中村さんはアーティストですから、普通はインタヴューされる立場ですが、3冊も本を出されてインタヴュー集をずっと作られてますよね。それもとっても珍しい。役割をこう逆転させることにも関心があるわけですか?
中村:ええ、そうです。話を聞きたいなあと思ったのが本当に始まりです。言語でしか伝わり難い部分もあるなって思った。人の話は、話を聞いて会うということも面白いし、それを活字にする面白さもある。それをやってみてこんなに大変なんだというのも分かった。僕らが情報として喋っていることはこれだけ多い情報量だったと。1時間のインタヴューでもの凄い数になるんですよ。枝葉がどんどん分かれていく。僕なりの勉強方法でもあった。実際に会ったことのない人に、名前だけ知ってる人に、アポとって会いに行く。初めて顔見て、「あっ、○○さんてこんな顏してたのか」とか、思うじゃないですか。普通だったら絶対に会わないような人もいる。パーティーだと、せいぜい「こんにちは」言う程度。作家の作品見ても作品に対してストレートに言わないで、「う〜ん、そうねえ」なんて言ってるだけで終わりですから。なのでもっと真剣に関わりたい、真剣に話をしてみたい、例え1時間でも、というのが動機です。
岡部:それはこうして中村さんにお会いしている私たちの動機でもありますけれども。
中村:インタヴューを、僕はもっと授業で積極的に取り入れるべきだと思います。
岡部:そうなんですけど、課外授業になるからなかなか難しいところもありますねえ。
中村:うんうん。単に親でも兄妹でも、一回インタヴューしてみるといい。そうやって言い難い部分をポロっと言ったりだとか。それで何かぶつかったりして。
岡部:コミュニケーションの最初の部分ですよね。
中村:アートは何か言い難い部分でも伝えたりとか、感じ難い部分でも感じたりしなきゃいけない。ひとつ特殊な技能を持たなきゃいけないと思うんです。技能っていったら変だけど、能力っていってもいいんだけど。ぼーっと見てるなかでもやっぱり何か自分だけが感じるものを感じて、その感じた部分を人に伝えないといけない。それは僕はトレーニングだと思うんですよ。訓練してできるもので、訓練しないとできない。やっぱり自分自身が鍛えられてきたように、韓国に行って、それまで引っ込み思案だったのが人前で喋るようになったとか(笑)。韓国での生活で、僕は3年間徹底的に鍛えられた。言語から思想から、生活態度も含めて。
岡部:だからハングルもできるんですね。
中村:ええ。いつの間にかしゃべれるようになってました。今、4册目のインタヴュー集をやってます。癖になって、何かインタヴューしたいなあって疼くんですね(笑)。
岡部:分かる、分かる。やっぱり普通だと見えてこない部分が見えてくることもあるし。他にはない未踏の分野を開拓できるみたいな感じですよね。
中村:いやあ、ほんとね、ライフワークとしてやれるひとつの仕事ですよね。単に会って話を聞くだけでいいんです。
岡部:(学生に)何か中村さんに質問はありますか?
学生:なんで東京がテーマなのですか?実家は何処ですか?
中村:僕実家は秋田です。東京っていうか、まあ大学を選ぶ段階で必然的にそうなった。本当は教育学部なんかに行こうと思っていたんだけど。絵を描いてて描くこと面白いじゃないですか、それで高校の時に絵の方に行こうと思って。毎日キャンバスとイーゼル抱えて学校に行って、学校行かないでそのまま海の方に行って2泊3日の旅とか勝手にやってすごくロマンチックな(笑)。船とかねえ。海描くのがすごく好きだった。絵を描く人は、自分のことを一人で考える時間が多い。自画像とか描いたり、自分のことを見つめることが好きな人で、ナルシストが多いですよね。でも逆に、同時に観察することが好きなわけです。人を見たり風景を見て、ここが面白いとか思うわけ。それは観察能力がないと出来ない。あとは我慢とか持続力。ものを2日も3日4日もずうっと見続ける忍耐力、そういうのが必要。そのへんの所から入ってきているので、多分方向は間違ってないと思います。ただ最近は、例えば話すことが好きで、人とこう会って話したりして、例えば僕の作品でマクドナルドとかコンビニの仕事とか、ああいうのはやっぱり交渉能力がとても大切ですね。
岡部:あの作品を制作するにはかなり相手方の企業を説得する必要がありますでしょう。マクドナルドに直接話をしに行ってるわけですね?
中村:そうそう。もちろん。「おたくの看板を僕に使わせて下さい」と言ってるわけだから。しかも「アートで使わせて下さい」と。勝手にはできない。
岡部:著作権の問題がありますものね。
中村:著作権で一発でアウトですよ。今日も午前中じつは行ってたんですよ。帰りにマクドナルドのコーヒーカップも買って来た(笑)。
学生:ストラップもマクドナルドですね。
中村:ええ。よく見つけましたね。縁起を担いでるんですよ(笑)。まあ違いますけど。秋葉原TVなんかと同じなんですけど、例えばマクドナルドを見た時に、これを美術として考えたいと。そのためには何をしなくてはならないのか。どうすればアートとして成立するのか。そのことが逆に社会にどう還元できるのかを考えたい。一番良いのは、みんなが僕が思っているような視線を、例えばデータ化してインストールし、僕と同じ視線を持てるものがあればいい。すると何もしなくてアートを感じることができる。面白いとか、きれいとか思える。その中間のメディアを必要としなくなるわけですよ。ものを置かなくてもわかるわけだから。でもまだまだそういう時代ではないので、わざわざでっかいMぽんと目の前に置いて、ある体験をさせないと僕の考えていることは伝わり難いし、視線を共有できない。たぶん一度見ていただければ、東京都現代美術館の展覧会、見てないかな?
岡部:「低温火傷」ですね。SCAI THE BATHHOUSEのマクドナルドの個展も見てますよ。
中村:見てますか。一度体験するとやはり街のなかにあるマクドナルドのちょっと変わった見方が多分体験できると思う。その時の視線の共有の仕方がアートの可能性を示している。もちろん交渉の段階で、自分と一般の民間企業を頭を下げてでも繋ぐわけです。それがアートの中なのか外なのか。そうすると今度はアートと言われている枠や限界が見えてくる。「何でこれがアートなの?」という人から、「ああこれもアートなんだ」、「これじゃないと、アートじゃない」という人が出てくる。だから凄く楽しい作業ではある。僕はこうしたアートのプロセスが大事だと思っているわけです。例えば大企業の人が、「マクドナルドを使いたいんだとしたら使ってもいいよ」なんて言われて始めるなら、全然リアリティーがない。そこのラインは大事にしてます。
岡部:やはり最初は反対されました?「そんなの著作権があるからだめだよ」とか。
中村:もちろん、もちろん。コンビニの時にも、一番最初にセブンイレブンが一番大変でした。マクドナルドの場合には、セブンイレブンやローソンの前例としての写真があるので、分かりやすい。「おたくの看板を売って僕は儲けようとしてます」なんていうことではない。「アートとしてこれが成立するんですよ」と。だから「そのために協力してください」という言い方をしている。ただものを見ないと分からない。セブンイレブンの時に一番大変だったのは、コンビニは4社あり、同業他者ですからライバルなわけです。メセナでも同業他者には普通声をかけない。それを無視したやり方だった。
岡部:まず無視するという発想自体が浮かばないでしょう。だけど売るわけですね。売れた場合にはどうするんですか?著作権使用料としてコミッションを払うのですか?
中村:各メーカーごとに契約ないしは誓約書を交わしていてすべて条件付きです。展示する場所や販売対象などは誰でもよいとはかぎらないとかです。
岡部:コレクターが欲しいと言えば、売ることはできるわけですね?
中村:もちろん。でも、その場合はコレクターを選ぶわけです。一応僕とメーカーがOKならいい。でもディーリングで作品が流れたりするのは心配ですが。
岡部:売れてます?なんて聞いてしまって(笑)。
中村:う〜ん、小さいものはね。いやまだ倉庫にいっぱいありますね。大型のを買う人はそう簡単にいない。勇気無いでしょ。
岡部:美術館とかぐらいしかね。
中村:美術館でも並みの美術館は買えないでしょう。買えるもんなら買ってみろって思ってます(笑)。生きてる間に買ってみろと。まあそのぐらいの気持ちですよ。
岡部:コンビニやマクドナルドなどの作品には2つの見方があると思うんです。ひとつはアメリカの消費社会のいわゆるグローバリズム、資本主義の消費に対しての批判と、さらに類似する日本の状況に対する示唆。日本の作家がそれに対して行為をするということ自体における批判性、あるいは風刺。それともうひとつは、アートと同じように、20世紀のシンボルという意味での表象の意味を問いかけるという両義性ですか。こうした観点に関してはいかがですか?
中村:もちろんそれは美術作品ですから、そういう観点で見ることは、全く問題ないしそれが正しいと思います。ただ資本主義の言葉のところから派生するものは、たぶん美術という中ではとてもとても解決できない言葉の深さがあるわけです。それは経済学者とか、現場で経済を動かしている人たちの力がある。それこそセブンイレブンの社長の経済的な感覚は、僕が単に美術作品としてそれを風刺するような程度のことをしても、全く対抗できるものではないし、質としては全然違うものです。僕の興味は最初に言ったように、このローカルな都市の中でアートの生成を形成する要素とどのように出会い対峙しその価値を組み換えていくのか?そのローカルな要素の中から見いだされた社会性が、グローバルな意味でどのようなメッセージとして社会に還元できるのか?ですからセブイレブン等コンビニエンスストアは、やはり日本の文化圏だから飛躍的に展開してきた思考がある。言いかえるとここのローカルな場の特性からくるサスティナブルな意識が具現化している。そういう意味で僕と都市との距離感が必然的に見いだされてくる。それを大事にしたいと思いますね。
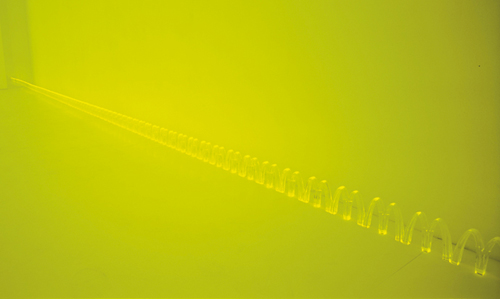
第49回ヴェニスビエンナーレ日本館2001 「QSC+mV/V.V」
© Masato Nakamura
| 特別協賛: | 日本マクドナルド株式会社 |
| 協賛: | キリンビール株式会社、松下電工株式会社 |
| 特別協力: | 直島コンテンポラリーアートミュージアム/ベネッセコーポレーション |
| 協力: | 東亜レジン株式会社、三菱レイヨン株式会社、 |
| 株式会社タキナミ、美術計画工房、株式会社白石コンテンポラリーアート |
岡部:秋葉原TVの後で、今はスキマプロジェクトを手がけられていて、秋葉原という地域に根ざしたプロジェクトとしては3回目ですね。
中村:そうですね。週の半分は秋葉原にいるじゃないですか。すると「あそこの看板変わったなあ」とか「店が変わったなあ」とか全部分かる。すごく変化が激しい。秋葉原ならではの価値、非常に批評性の高い街ですから。下手な商品を置いても誰も見向きもしない。また、おたくの人達が集まる街になってきている。アニメだとか、フィギアだとかが全国から集まってくる。もちろんコンピューターおたくの人達もいて、古い使えそうにもない基盤を、「おぉ」とか言って見てるわけで、僕はそこでアートを言わなければいけないわけですね。そういう人達に向かってだったらフィギアを使ってのアートなら、いとも簡単なわけです。でもそうではない方法で彼らを説得したいと思うし、そうではない方法で街と接するから、新しい価値が生まれてくる。もうひとつは、アーティストという職業的な倫理。アーティスト、キュレーター、プロデューサーといった職能はなんで分かれていったのか。例えば、映画産業では細分化されて、カメラを覗く人と監督とでは絶対的な権力の違いがある。でも、アートに関しては本当にあるのか?と。僕はいつも思う。お金を集めてくる人とアイディアを出す人が一緒でもいいだろうし、ものを手作りで作る人も一緒の価値観でいいだろうと。こうした職能分化の歴史が何か、その基準を僕は街に求めて、街を基準にして構図する感じにしないと、ハードだけで、管理主義的な部分だけでしかアートが語られなくなり、メッセージを伝えるための制度に移行しないと思う。もちろんその役割分担は、コマンドNの内部でもいろいろ毎日いろいろあるわけですけど。
岡部:みんなでディスカッションしたりするのですね。
中村:ええ。まだまだ未開発のジャンルですよ。ずーっと続いてますけど(笑)、建物もできて、作品も集まって、教育基盤も広がり、優秀な人がいっぱいでてきているけれども、仕事が無い。それは自分で仕事があるところに向かって無いと言ってるだけで、自分で仕事を見つけて、自分で生み出そうと思っていないからです。自分でやればいいと僕はいつも思っている。コマンドNに来る人も、「キュレーターになりたいんですけれども、どうしたらいいんですかね?」と言う。そんなの自分でやんなさい、展覧会を自分で一本つくればいいでしょ。建物に、制度に依存しているから良くないんだと思う。学校の中で、学校を出て外で、どんどんやればいい。するとおのずから自分の人間関係ができてくるし、どこが問題なのか分かってくるし、本当に自分に向いてるかどうかも分かってくる。凄く初歩的な段階ですけどね。
岡部:私もそう思います。秋葉原の事務所は地域の人が無料で貸して下さっているのですか?
中村:そうです。千代田区です。街づくり推進公社の持ちビルです。一応一年ごとの契約で、来年いられるかどうか分からない状況ですが。
岡部:そうですか。それはかなり辛いところですね。
中村:僕らも地域に対してすごくやってますけど、役所から見ると、感じ難い部分があるみたいです。例えば小学生とワークショップをするとか、書面にした時に役所の上の人が、「おお、いいことやってるじゃない」って、ハンコをポンと押しやすい分かりやすい事をしないとだめみたいですね。秋葉原TVはすごく説得力があったみたいですが、スキマプロジェクトのように、今小さい展覧会を何個かやってても、見にこないですからね。何それみたいな(笑)。
岡部:例えばこうした展覧会をひとつ実現するとき、オーガナイズもファンドレージングも分担するのですか?
中村:毎回言い出した人がディレクションでしきってますが、資金は自分たちで探して、あとはコマンドN基金から出してます。僕らがお金を出して、毎月お金をプ−ルしてるんですよ。基本的には電話代や電気代だとか、最低限出ていくお金があり、家賃が無いので、今は各自1万円以下ですが。家賃が必要だった頃は、本当にすごかった。「一体何のために働いてんだ」って(笑)。「ミルク代どうすんの?」って家内に言われて(笑)。
岡部:たいへんですねえ。みんなで共同で行うプロジェクトは、自分自身でやる作家活動とは、別な形になりますから。でも自分自身もいろいろ得るところがあるし、世界中の大勢の人との関わりも生まれ、ネットワークもできる。べつの刺激を受けますよね。
中村:アーティストのネットワークに関して最近思うのは、やってる人同志の共有する意識の存在で、不思議だけれど、アーティストランスペースは、世界中にいっぱいあり、すぐに繋がってくれるんです。
岡部:カナダにたくさんありますよね。今、カナダのバンフというアーティスト・レジデンスに日本から作家を送り出すプロジェクトを手がけているのですが、中村さんはこれまで、韓国以外でアーティスト・レジデンスのご経験はあるのですか?
中村:=香港に1年近く住んでいた事があります。でも1ヶ月で飽きて、まあアート以外は街としては面白いです。これからメルボルンのレジデンスに行く予定です。ヨーロッパとかにも、そろそろ行きたいなあと思ってますけど。
岡部:レジデンスって大事ですよね。
中村:ええ。自分の住んでるエリアを、僕は学生の頃から大事に考えるべきだと思っていて、住んでる環境の出来事の重要性。その環境を選ぶことが大事。でソウルかニューヨークかという時にソウルを選ぶ。その先はソウルに任せる。東京にいることで、東京に任せる部分もある。そういう影響の度合いを考えると、まず自分達が住んでいるアジア圏のエリアの影響をベースにして、そこから40歳以降に自分を立脚するステージを次に結び付けたいというのが正直なところです。
学生:メッセージとしてはこの先、東京よりももっと広いものにつながっていくんですか?
中村:う〜ん。僕個人の、多分その活動が広がっていけばそうなるだろうし。コマンドNとしても違う意味で街と関われるポジションになれば、発言権も出てくると思う。もちろん、全てアートというフィールドの中でやっていきたいけれども、例えば建築家がやっているような建物を建てる職業だとか、都市を俯瞰して見るというやり方とは違う可能性が絶対あるはずで、その道をこうつついているような感じはします。いわゆるゼネコン的なパブリックアートとは違う方法でアートの機能のさせ方を将来的に定着させたい、考えたい。
岡部:コマンドNの企画も国際的ですが、いわゆるビエンナーレとかトリエンナーレなどの国際展に中村さん参加なさったこともありますよね。その経験についてお聞きできますか?
中村:参加するのと自分でやるのは全然意識が違いますよね。オーストラリアのブリスベンでやったアジア・パシフィック・トリエンナーレは最悪で、もう2度と行きたくないなと思った。美術という言葉が感じられるような展覧会ではなかった。逆にタイのチェンマイでやった、チェンマイ・ソーシャル・インスタレーションという展覧会はものすごく楽しくて。作家の仕事としてよかったと思えるくらいでした。ほとんど自費で行ってる部分もあるんですが。その違いは、非常に大きいですね。
岡部:それを知りたいんです。どうして良くなかったのか、実際には作家ではないと分からない部分がありますからね。
中村:例えば、ブリスベンの場合は選ばれた段階で、日本人のキュレーターの人がいるわけです。まあその段階では問題は無い。ただ問題なのは、向こう側のキュレーションのポジションです。テーマを設けて、約70人ぐらいの作家を全世界から集めて、日本からは3人行った。飽くまで作家が主体ではなくて、キュレーションが主体の展覧会なんですよ。しかも、インターナショナルなところで政治的な場になる。日本対韓国だとか。もし、それでも楽しめるとするならば、いろいろなステップが有るはずで、例えば下見に行って、場所を確認しながら、何の作品を作ろうかとか。現地で、キュレーターの人に会って、僕はこういう作品をここにこういう風にやりたいと思うというのが筋ですよね。もちろん費用的な部分は美術館持ちで。でもブリスベンの場合は、そういう過程は全く無く、あなたは特別に選ばれましたみたいな感じで進んで、かつ、アーティストフィー等も非常に条件が悪い。まあ、1万円ちょっとあるだけいいですけど。結局、膨大な作品を送ったけど、作品に対する理解度が無かったということが現地に行って分かった。
岡部:作品がかなり痛んでしまったのですか?
中村:かなり痛んで。で、「壊れやすいものなんだからしょうがないんですか?」っていうようなファックスが来たりとか。もうとてもとても、何のためにやってんのって感じです。協力したにもかかわらず、協力した気持ちに対してのケアが全く無い。アートを利用したにすぎない。
岡部:アーティストへのサポートを考えていないわけですね。事業みたいな感じですかね。
中村:事業ですよ。主体がアーティストの考えではなくて、飽くまで展覧会という、しかも国際展という枠。その美術館は日頃何やってるかというと、現代美術ではなく近代や印象派的なもので、学芸員も途中で担当が変わったり、マイナスの部分ばっかりがめだった。こういう展覧会は参加したくないですね。
岡部:チェンマイの展覧会はどうしてそんなに素晴らしかったのですか?自費で行ったにもかかわらず。
中村:展覧会は楽しいけれども、同時にリスクを背負うこと。チェンマイの場合は、現地滞在で、もう3日で作ったわけです(笑)。でもそのリスク以上に楽しかった。街が面白かったし、作品の設置のひとつひとつに、作るってことに対してもシンパシーを共有する人が現地に居たし、お客さんも街自体も。作ることも、展覧会という枠も楽しめた。バスを3台ぐらいチャーターして、白バイ誘導で、一個一個作品を見て街を練り歩く。考えられないでしょ。怠惰でだらしない格好したおやじ達が作品を見て、「これが作品か」みたいな感じで、「じゃあ次に行きまぁすよー」みたいな観賞会があったり。途中の昼食では、タイ料理のおいしいもの食べたり、最高(笑)。
岡部:チェンマイでは、制作費ぐらいは先方が出してくれたのですか?
中村:いやいや自分で。自分で楽しむ方法を探しながらやってるってことですね。やはり、僕達はものを作るってことが生活なわけだから。その生活が立脚しないと続かない。
岡部:ええ、分かります。
中村:だから、それはそれでいい。僕来年ヴェネチア・ビエンナーレの日本館に参加する作家に選ばれたんです。
岡部:ええ、よかったですね。
中村:ヴェネチアでやりたいと思ったのは、そこにまだまだ魅力があるから。コミッショナーの逢坂恵美子さんや他の出品作家と一緒に、主体的なメッセージを組み立て実現できる可能性があるからです。下見をした時に、ヴェネチアの街がすごくきれいなことと、日本館や各国のパビリオンの在り方の不自然さなど、ここでやれるんだったら面白いなあと思いました。
岡部:ヴェネチア・ビエンナーレでは大勢の人が見てくれますしね。
中村:国際展のあり方は、もうひとつ、横浜トリエンナーレがありますよね。ふたを開けてみないと分からないですが、もちろん、期待する部分もある。僕らが秋葉原に対して、こだわっているような考え方を、できれば横浜というステージでやる。もう少し広い、東京圏というか、その中で考えられるキュレーションをしないと、ただ単に有名な人を集めてきて、「おもしろいだろう」と、「俺が企画したんだから面白いに決まってるんだ」って言って終わりになる。そうなると、面白い人達のためだけの展覧会という構図になり、またひとつのヒエラルキーを作るだけですよ。アーティストは、もっと裾が広くて、面白い人も面白くない人も居て、それでいて初めてシーンというものが成り立つわけじゃないですか。そのシーンに対しての何の関係もないイベントになってしまう。そういうのではないあり方になってほしいと思ってます。それが、国際展の課題でもありますよね。国際の意味が必要でしょう。
岡部:そうですね。こういうことは、みんなでしっかり考えていくべきだと思います。今日はありがとうございました。
(テープ起こし担当:國井万紗子)
↑トップへ戻る